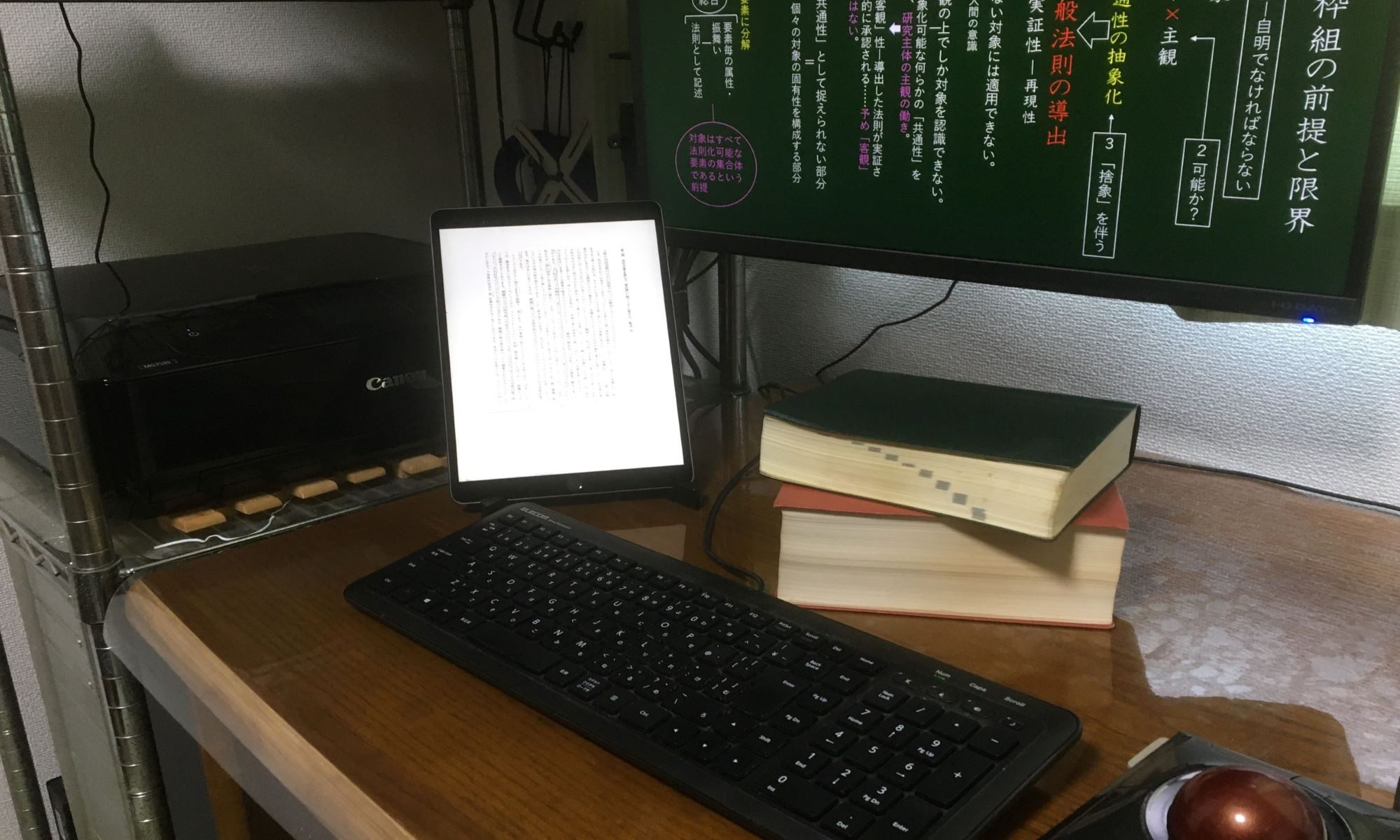今回の言わずもがなのお喋りのネタはマデレーン・オルブライト『ファシズム 警告の書』(2019)である。ムッソリーニ、ヒトラー、スターリンといった、言わずと知れたファシズム史の「スター」の行跡の紹介・分析を経て、戦後から現代に到るファシスト的政治家の人物伝、という趣の書だ。たとえばハンナ・アーレントの名著『全体主義の起源』のように、「反ユダヤ主義」や「植民地主義」などファシズム運動をもたらした歴史的背景を丁寧に分析するわけではなく、またW.ラカーの『ファシズム 昨日・今日・明日』のような、世界中に広汎にみられるファシズム的運動の紹介・分析を主眼とした書でもない。過去のファシストについて特に目新しい知見が示されているわけでもないが、しかし、現代が新たなファシズムの時代の予兆と思えるようなサインに満ちた時代であることが実感できる、必読の書である。著者がこの書をものした契機がトランプ政権の登場であることが序文で触れられているが、なにもこの張子の虎(ンプ)だけではない。自己が疎外されていると感じる人々が多数存在する社会は、アメリカだけではないだろう。ファシズムはそのような状況で人々の心のなかに兆してくる欲動を餌に、(人々の気持ちを代弁するかに装って)成長するという「常識」をもう一度銘記する必要があるだろう。特に政府が無策な、あるいは腐敗している国家においては要注意である。どことは言わないが。
ファシズムというのは難しい概念で、「人の数ほど定義がある」といっても良いくらいだ。それもそのはず、「カント哲学」「実存主義」「構造主義」などと違って、「ファシズム」という具体的な思想は存在しない。『ファシズム 警告の書』にはこうある。
「私(マデレーンおばさんである)が考えるファシストとは、特定の集団や国家に自分を重ね合わせてみずからをその代弁者とみなし、人々の権利に無関心で、目標達成のためには暴力も辞さずにどんなことでもする人物だ。」(白川貴子・高取芳彦訳)
これを筆者流に解釈すれば、特定の集団や国家の標榜する理念をあたかも救世主であるかのように賛美し、権威主義的にそれへの同調を(ときに暴力を以て)他者に強要、その内面まで規制して国家・集団への奉仕を求める人物、ということになる。つまり国家・集団の唱える主張の具体的な内容(それは民族主義でも共産主義でも、他の主張でもあり得る――もしかしたら民主主義を騙るかもしれない)は問わない。「ファシスト」は実在しても具体的内容を伴った「ファシズム」という思想は存在しない。「ファシズム」とはむしろ、そのような人物や集団の行動様式をいう言葉なのだろう。
著者のマデレーン・オルブライトはチェコスロヴァキア出身のユダヤ系アメリカ人なのだそうだ。幼い頃からファシズム(ナチスとスターリン)の弾圧を逃れて家族とともに2度も亡命した経歴を持つ人で、いくら父親が外交官だったとはいえ、そのような中で学問に勤しみ、第2次クリントン政権でアメリカ史上初の女性国務長官となった人なのだから、いかに優秀な人物であるかわかるだろう。『ファシズム 警告の書』後半の、国務長官時代に交渉の機会をもったユーゴスラヴィアのミロシェビッチ、ロシアのプーチン、トルコのエルドアンなど、ファシスト的傾向をもった政治家についての観察、分析は非常に鋭いものを感じさせる。たとえばプーチンについて「プーチンは完全なファシストではない。そうなる必要を感じていないからだ。その代わり、首相や大統領として、スターリンの全体主義の教科書をめくり、都合良く使えそうな部分にアンダーラインを引いてきた。(中略)プーチンの望みは、自らの統治下にある人々に、彼が政治的に無敵の存在だと信じ込ませることだ。困難(あるいは危険)を顧みない潜在的な政敵が全国規模の本格的な対抗勢力を結集することのないよう、その気勢を削ぐことにいつも力を費やしている。(中略)プーチンは自らの魅力を維持するため、特定のイデオロギーや党派と深く結びつくことを避け、国全体の顔としてのプーチン像を描こうとしている。」(下線は筆者による)
このような、海千山千の妖怪が相手である。親愛なるわが国のス×ーリンでは少々役者不足かもしれない。