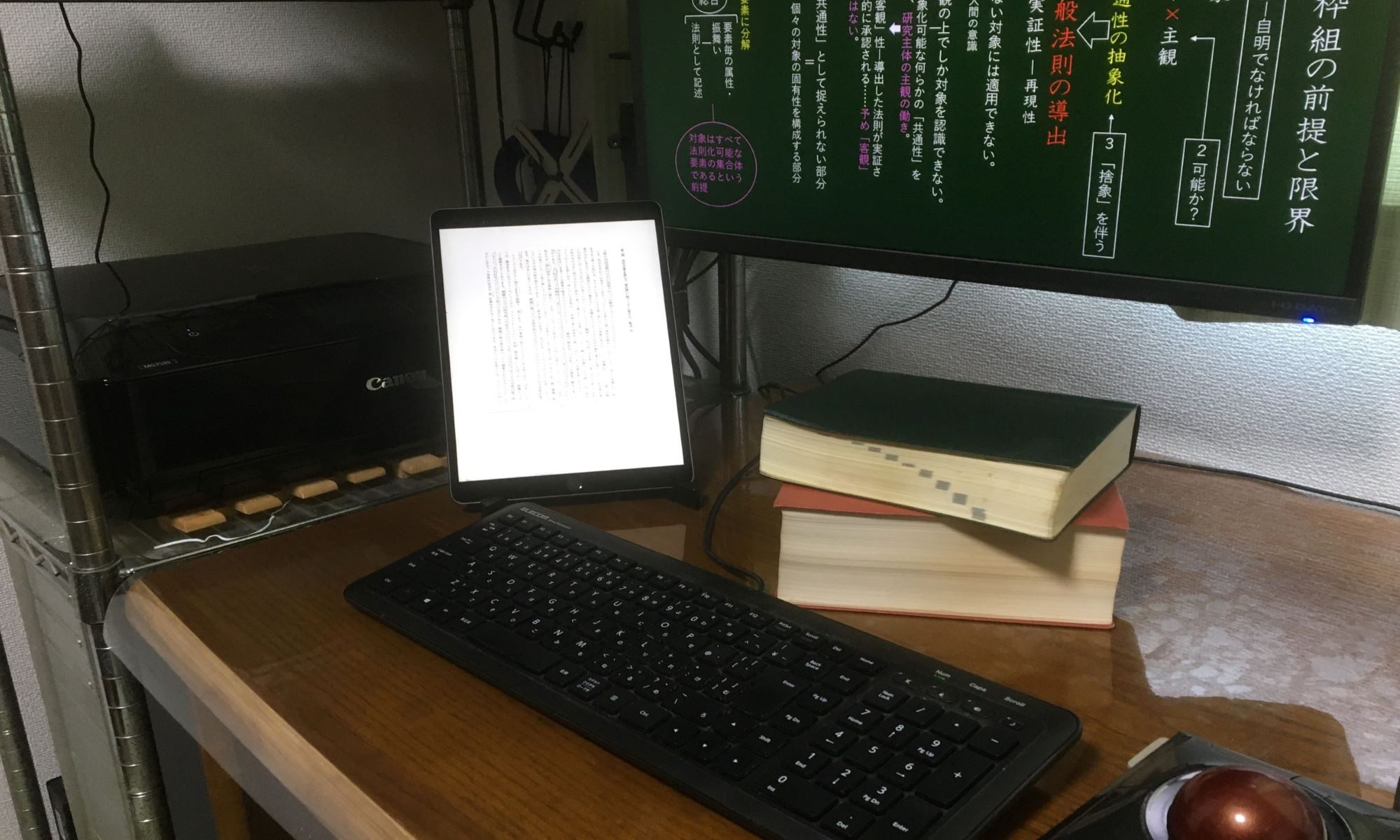『特高月報』というのをご存知だろうか? 戦前~戦中に、民間の思想弾圧に「大活躍」した特別高等警察(特高)の遺した記録だが、今回話のタネとする書の編著者、髙井ホアン氏による紹介を引用しよう。
「特高警察および憲兵隊は戦前、まさにその職務のために膨大な記録を残した。その中には、共産党関係への膨大な監視記録、小林多喜二が築地警察署で『死亡』した有名な事件、またキリスト教を初めとする宗教者への圧力や、水平社(部落解放同盟)への監視の記録がある。そして、それらに属していない市井の人々を監視した記録もある。(中略)あらゆる物を監視し続けた組織は、落書きから子どもの替え歌まで権力の脅威となるもの全てを弾圧するに際して記録した。それが特高月報であり、憲兵隊記録である。」(『戦前不敬発言大全』まえがき)
角書きに「戦前ホンネ発言大全」と題された『戦前不敬発言大全』『戦前反戦発言大全』は、おもにその膨大な『特高月報』を博捜し、記録された当時の一般庶民の「不敬」「反戦」発言を集成した労作である。昭和十年代の記録が中心なので、「戦前」というよりむしろ「戦中」としたほうが相応しいが、思想の弾圧が徐々に苛烈を極めていった時期の記録だけに、抑圧された無名の人々のルサンチマンが生々しく示されている(なにしろ権力の側が自分たちにとって都合の悪い発言を記録したものなのだから、資料としても信頼性が高いのではないか)。編著者の言う通り、「そこには、皮肉にも権力の監視を通して、当時を生きた市民の様々な姿が残って」いて、非常に興味深いものがある。
そこにあるのは、公衆便所の落書きレベルの下品極まる発言から、デマ、根拠不明の陰謀論や意味不明の電波系発言、そして現在の目から見ても至極まっとうな抗議や意見に至るまで。実に多様な「発言」を通覧すると、ほとんどカオスを思わせるものがある。また、当時まだナチス統治下のドイツやスターリン体制下のソ連の内情が知られていなかったことから、ヒトラーやスターリンを支持する発言や落書きがいくつも報告されているのも時代を感じさせる。『特高月報』ではその後「発言」者がどのような処分を受けたかについても記録されているとのことで、この本では確認できる範囲でそれも付記されている(処分の基準が必ずしも一定していないように見えるのも面白い)。編著者高井氏による「コラム」も、当時の言論弾圧に関わる様々な事例(有名な事件から巷間の噂やデマまで)の紹介も、(私などが言うのも何だが)概ね適切で、背景となる時代相の理解に役立つだろう(一つだけ難を言わせてもらうと誤植が目立つ。『特高月報』からの引用部分については原資料の誤字という可能性も考えられるが、氏のコラムにも散見されるので原稿でのミスか、印刷屋のミスか。「虞(おそれ)あり」のはずが「虜あり」となっていたりするのでワープロの変換ミスばかりではなさそうである)。
品格を重んずる当ブログの方針からして、下品極まる表現をも含む「発言」の一々を引用して紹介できないのはとてもザンネンであるが、中でも胸を衝かれたのは『特高月報』昭和12年11月号所載の次の記事である。
高松市松島町 戦死者常二妻 柴佳子(22)
本名は戦死者の妻女にして其の遺子の愛に引かされ左の如き呪詛的通信を友人宛発送したる事実あり。「毎日の様に子供が『お父さんは何時帰るの』と聞かれる時の私の切なさよ。仏壇の前に連れて行き『ケンマンスと拝んでみたら帰るよ』と言ったら毎日の様に仏壇へ行って拝み他所から何か貰ったら直ぐ仏壇に供へて拝み『お父さん帰らないなア』と私に泣きつかれる時の切なさよ。嗚呼片輪でも何でもよい生きてゐてくれさへしたら今度の戦争さへなかったら他所様と同じ様に一家三人が仲良く暮らされるのに戦争があったばかりに坊のお父さんは亡くなったと思へば戦争がうらめしうございます」
この文面を読む辛さばかりではない。このような私信まで監視され、記録されていた社会の異常さを思うと今更ながら暗澹たる気分になる。特高警察は一々開封して中身を確認していたのだろうか。それともこの手紙を受け取った「友人」か、あるいは何らかの事情で内容を知った者がご注進におよんだのだろうか。いずれにせよ二度とこのような社会にはなってほしくないものだ(高井氏の注記によると、この件についての処分は『特高月報』に記載されていないようだ。さすがに人情として処罰はできなかったのだろうか)。
近年は「新内閣発足」「内閣改造」とやらの度に閣僚となった御仁が問題発言をする、というのが恒例行事と化している観があるが、彼らは今の時代に感謝すべきかもしれないね。市井の人間の何気ない発言まで監視されている時代に比べれば、政治家の発言が羽毛のごとく軽くなっている時代のほうがまだマシなのかもしれない(それにしても、何で彼らは閣僚などという、私的な会合での発言までも問題視される立場になりたがるのだろうか。まったく理解できない。好きなことを言いたければ、授業で少々放言をしても生徒に「困ったヲジサン」と思われるだけで許してもらえる私のような受験屋にでもなればよいのに)。