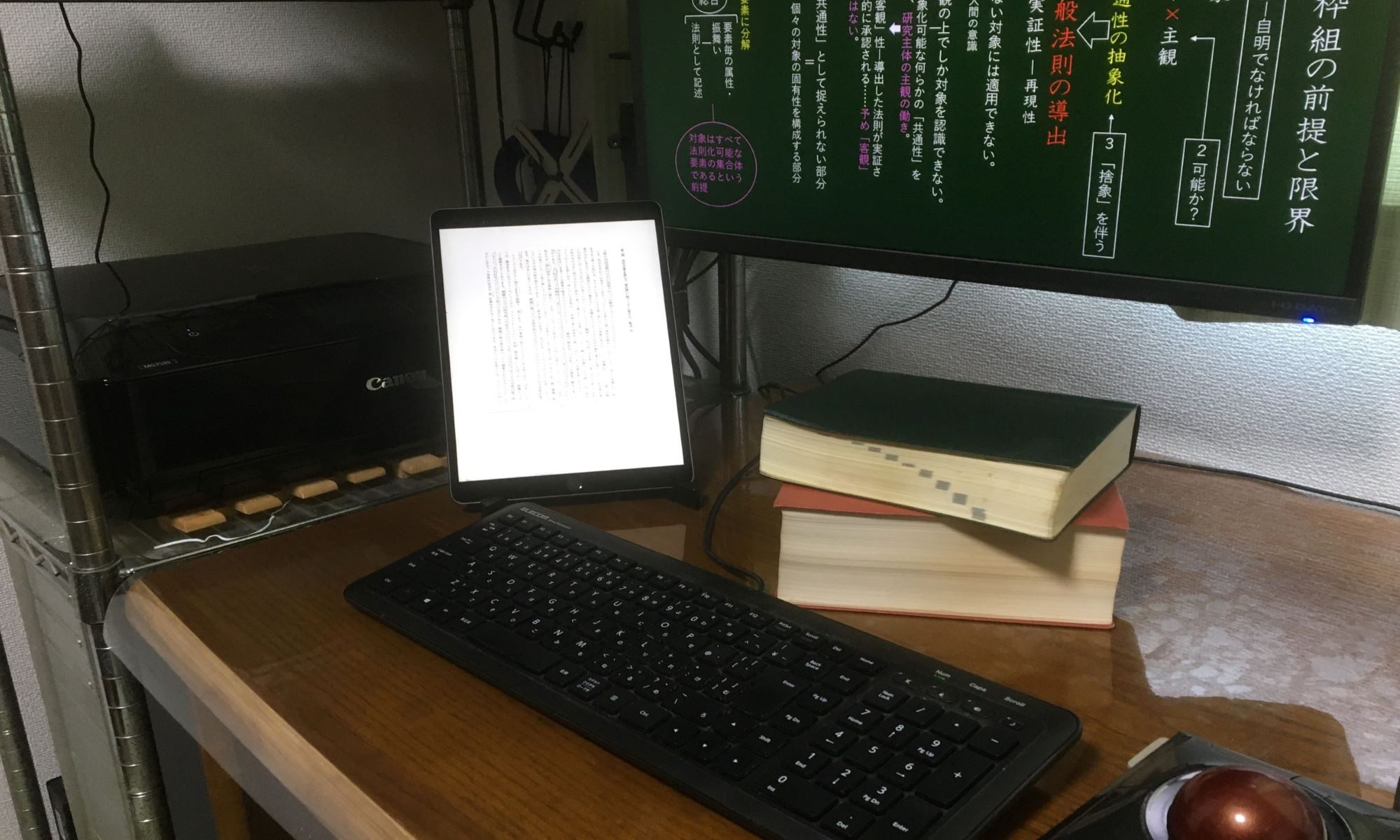たまたま昔の探偵映画を再見して、立て続けに見たのが『不連続殺人事件』(1977)と『犬神家の一族』(1976)であった。『不連続殺人事件』は坂口安吾原作で曾根中生監督、『犬神家の一族』は横溝正史原作で市川崑監督、名探偵役はそれぞれ小坂一也と石坂浩二と、いずれも有名な作品だが、この二つ、いくつかの共通点がある。怪しげな登場人物と複雑な人間関係、趣向を凝らしたトリック、それを見事に解き明かす名探偵という、探偵小説の定番を履んでいることはいうまでもないが、両作とも真犯人が予定の殺人をすべて実行した後に謎が解明されること(つまり犯人は目的を果たしてしまうわけだ)、最後の殺人がなされる(つまりこれで目的達成)とき名探偵が不在(証拠捜しに別の土地に出かけている)で、戻ってきてから最後の殺人が実行されたことを知って自分の不敏を恥じること、さらに真相の露見を知った真犯人が衆人環視の中、隙を見て服毒死し、名探偵が「しまった」と叫ぶこと。これでは何のための名探偵かわからないね、と言われてしまいそうだが、考えてみれば事件を予見してそれを防ぐために果敢に行動し、見事犯罪を未然に防いだ、というのではまるで『案内手本通人蔵(あなでほんつうじんぐら)』になってしまって、少なくともサスペンスにはならないだろう。
『案内手本通人蔵』というのは安永八年(1779)刊行の黄表紙で、題名からもわかるとおり『仮名手本忠臣蔵』のパロディである。作者は朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ。これはもちろん戯号で、ご本人は秋田藩留守居役という立派な身分の武士)。どんな話かというと、『忠臣蔵』の悲劇は塩冶判官、といっても何のことだかわからない人のために解説すると、江戸時代は、同時代の事件をそのままネタにしては幕府の禁に触れるので『忠臣蔵』は室町時代を舞台としている。したがって登場人物も史実とは別の人物が宛てられており、浅野内匠頭は塩冶判官、吉良上野介は足利尊氏の執事高師直、大石内蔵助は大星由良之助となっている。その塩冶判官が通(つう。人情や社会の機微に通じていること)でなかったことが悲劇の原因として、序文に曰く、
「仮名手本忠臣蔵を按ずるに、大星が忠義抜群なりといえども、もとは塩冶の不通により、かつ初めの賄(まいない)の薄きより起れり。これ世の中の案内(あな)を知らぬ故なり。されば世の中の案内を知るを通といふ。世の人みな通なれば、世の中に闘諍(いざこざ)なく、ますます太平なり。」
つまり大石を初めとする四十七士の忠義は抜群でも、もとは浅野内匠頭が通でなく、また世間知らずにも吉良上野介への賄賂が少なかったことによる悲劇であり、世間の人がみな通なら、つまらぬ争いもなく太平だ、という堂々たる思想のもと、『忠臣蔵』の名場面を一々パロディにしてゆくのである。たとえば塩冶判官(内匠頭)が師直(上野介)に額傷をつける場面を、お軽勘平が逢引していちゃついていたはずみに簪を落とし(『忠臣蔵』で、お軽が簪を落とすのは七段目「祇園一力茶屋」の場)、それで師直の額に傷がついたが、師直も通人なので偶然瓦が落ちて額傷がついたことにして二人をかばってやる。塩冶判官はそれを申し訳なく思って二人を勘当するという話に改変し、そこで登場人物の一人に「まだ七段目でもないに簪を落とすとは粗相なことだ」と言わせたりする。つまりこれといった事件も起らず、したがって何の悲劇もない。また物語の序段で饗応を受ける足利直義について、
「直義公旦那株ゆゑ、通といふほどのことはましまさねども、無理通(=通人ぶること)のこじつけにて悪しき事もただよしただよしとばかり仰せらるるかぶなれば、足利直義とは申すとかや」
と愚にもつかない駄洒落をかます。そして最後に「気を通に持て」という尤もらしい格言。
どうです。くだらない話でしょう。朋誠堂喜三二には他にも、民話「かちかち山」の後日譚として、兎にひどい目に遭った狸の息子が兎を親の敵と付け狙う『親敵討腹鼓(おやのかたきうてやはらつづみ)』というのがあって、これもパロディ満載の作品なのだが、苦労の甲斐あって狸の息子は兎を追い詰め、ズンばらりと一刀両断、見事本懐を遂げる。斬られた兎は黒い鳥と白い鳥になって飛んでゆきました、という話で、身分あるお武家様が、このどうでもよい駄洒落をオチにするためにわざわざ作品を書く。それはそれは良い時代でありました。