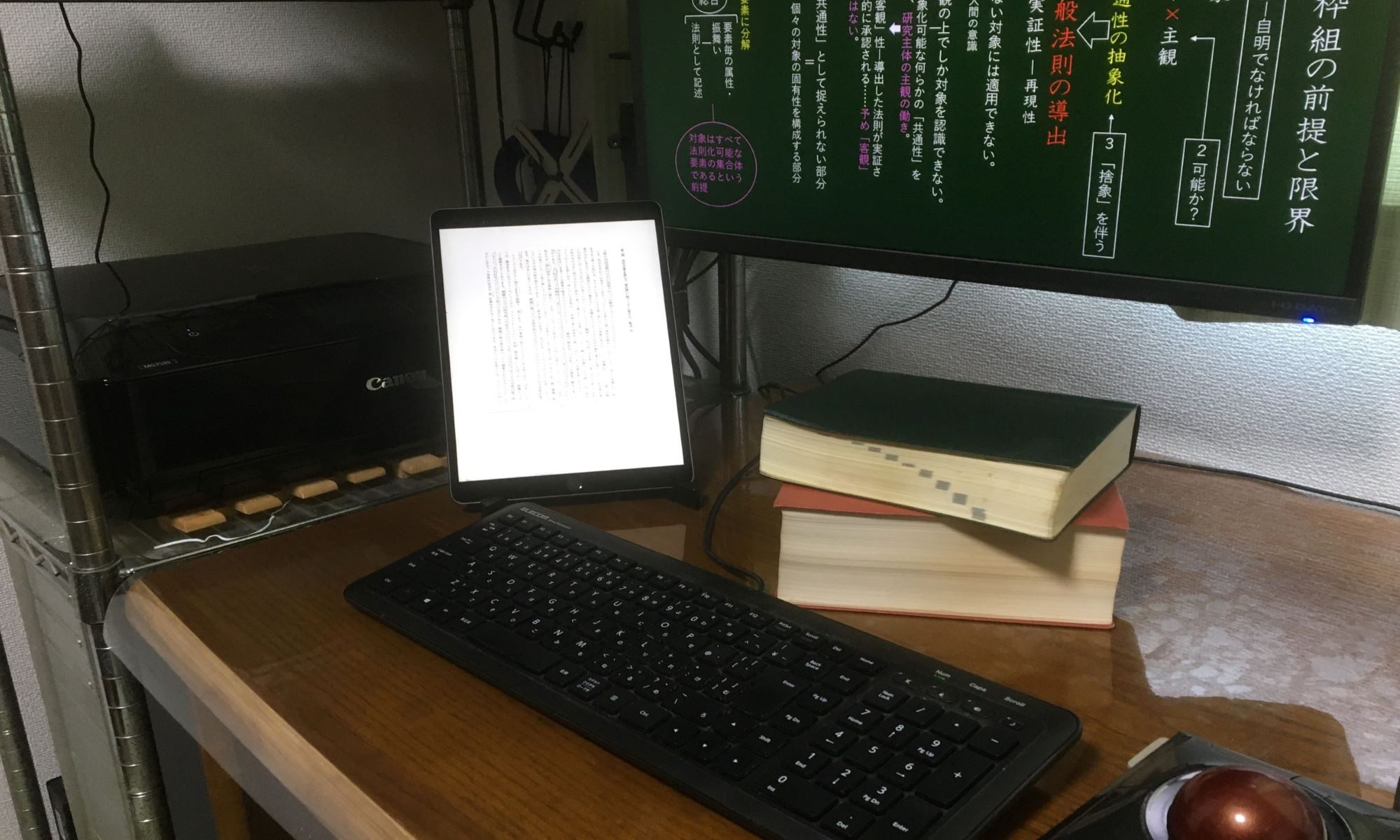『怪人マブゼ博士』(『マブゼ博士の遺言』)は、『ドクトル・マブゼ』10年後の続編である。10年も経てば、作家の問題意識もそれなりの変容を遂げるだろう。それは進化・発展と呼ばれるべきものである場合もあれば、退行・堕落と呼ばれる場合もあるだろう。ラングと脚本家ハルボウのコンビはどうだろうか。
警部のもとに元部下からの電話が入る。「偽札工場を見つけた。」だが肝心のことを聞こうとした途端、部下の悲鳴とともに電話は切れる。駆けつけてみると部下の部屋はもぬけの殻で、部下は発狂状態で精神病院に収容されていた。彼は病院でも警部に連絡を取ろうとする電話の一人芝居を続けているが、声を掛けると恐怖に顔を引きつらせ、幼児の歌を唱い始める。彼の遺した手がかりから、捜査を進める警部。折しも、10年前に悪事が露見し、発狂状態で見つかったマブゼが狂気の中で記したメモの通りの犯罪が新聞を賑わしていた……。
と、サスペンス調の物語だが、サスペンスとして見ると「リアリティのない作品」ということになってしまうかもしれない。なにしろマブゼを担当する精神科医が、死んだマブゼの霊みたいなものを見たり、それが彼に憑依する場面がクライマックス・シーンなののだから。
言葉の映画
これは最初から最後まで「言葉」が鍵となる作品である。冒頭、偽札工場の耳を圧する轟音の中、潜入した元部下とマブゼの手下とのそれぞれ無言の仕草(前作『ドクトル・マブゼ』はサイレントであったが、この作品はラングにとって『M』に続くトーキーである)、電話で肝心のことを言葉にしようとした瞬間に襲われ、発狂してその言葉を口にできなくなってしまった元部下、廃人同然となってメモの言葉のみが意味あるものとなったマブゼ、そのマブゼの意志を代行(?)し、手下に鉄の規律を以て犯罪の実行を指示する謎の黒幕が、実際にはスピーカーとマイク―つまり口と耳、言葉を発する器官と言葉を捉える器官―を付けただけの薄っぺらい板の人型でしかないこと……。すでに前作『ドクトル・マブゼ』でも、マブゼを追い詰めようとするヴェンク検事を窮地に陥れるのが、マブゼの言葉の暗示による催眠術であった(ツィ・ナン・フ―tsi nam fu 済南府のことらしい―とメリオール、いずれも地名であることに何か意味があるのだろうか)。物語のクライマックスは、死んだはずのマブゼの霊のごときもの(つまり精神であろう)が、彼を診ていた精神科医に取憑き、マブゼの意志が精神科医に転移する場面である。ここでマブゼは精神科医を相手に、初めて自らの目的を語る。DVDの附録のブックレットには、字幕では字数の制約によって完全に訳出できなかったというマブゼの言葉の忠実な訳文が紹介されている。それを引用しよう。
「人間の魂のもっとも奥底の部分を、究明しがたく一見無意味な犯罪で震えあがらせなければならない。犯罪は何人にも益せず、不安と恐怖を広めることだけを唯一の目的とする。なぜなら犯罪の最終的な意味とは、限りなき犯罪の支配を打ち立て、滅亡を運命づけられたこの世界で破壊された理想を基礎として、完全なる不安定と無政府状態を作り出すことにあるからである。人間が犯罪のテロルによって支配され、恐怖と驚嘆によって正気を失うとき、そしてカオスが至高の掟へと高められるとき、犯罪の支配のときが訪れる。」(渋谷哲也訳)
完全な、純粋テロリストの登場である。犯罪の支配と、すべてを混沌へと還元しようとする意志。廃人同然で、すでに肉体の意味を失っていたマブゼに遺されていたのはこの強烈な意志と、それを表明する遺言(メモに記された犯罪計画と、精神科医に語った言葉)だけである。いわば言葉だけの存在となったマブゼに、精神科医は呪縛され、彼の犯罪計画の実行に着手する。
フリードリヒ(?)
言葉による呪縛。人間が言葉によって世界を認識し、言葉によって思考する存在である以上、言葉の持つ人間への規制力はいつの時代でも強力で、場合によっては危険なものであろう。ドイツ国内でナチスが完全に勝利する直前に制作され、公開直前に上映禁止処分を喰らってラングがドイツを脱出する直接のきっかけとなった作品だが、現代のわれわれが鑑賞する際、何もヒトラーにのみ結びつけて解釈する必要もないだろう。『怪人マブゼ博士』(原題は『Das Testament des Dr.Mabuse』、『マブゼ博士の遺言』。邦題よりこちらのほうがより直接的に内容を表現している)は、おそらくいつの時代においても「今日的」な主題を扱った、重要な作品のひとつであろう。
などととりとめもないことを考えていると、「マブゼ」はヒトラーや(ラングの語っていた)「ニーチェの『超人』の悪い例」などではなく、ニーチェその人であるような気もしてくる。通俗的秩序の中に安住する大衆を呪詛し続け、晩年に狂気に陥った彼の言葉は、今でも若い連中に中毒患者・模倣者を作り出し続けているのだから。
マブゼを演ずるのは前作に続いてルドルフ・クライン・ロッゲ。ただし、前作のような大活躍と違って今回は精神病院の廃人だから、あまり彼の演技は目立たない。かわりに魅力的なキャラクターを演ずるのは、物語の狂言廻し的存在ローマン警部役のオットー・ヴェルニケ。ローマン警部の、傲岸でありながら愛嬌のある個性を好演している。
また、前作でマブゼに「表現主義など遊びですな」という台詞を吐かせていたラングだが、この作品には『カリガリ博士』を思わせるような不均衡な構図が何カ所か出てくる。ラングの遊び心の発露だろう。
なお、ラングは戦後『マブゼ博士と千の目』という、今度は監視社会をテーマにした作品を遺しているそうだ。まだ未見だが、いずれ観てみたい作品である。