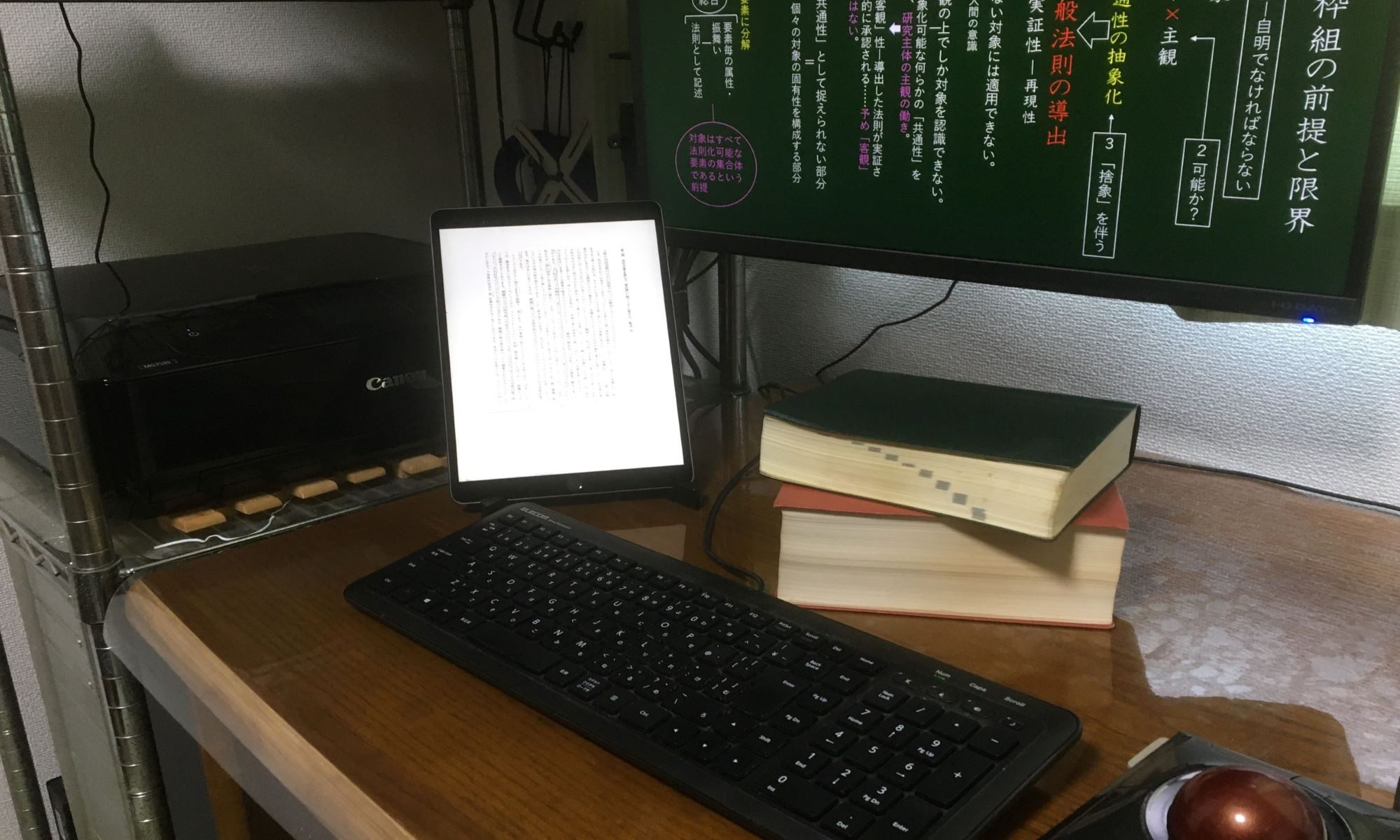これは学習塾の宣伝ブログなので、具体的なことを書くのは差し控えるが、かつて東映という映画会社は「エロ・グロ路線」と言われた一連のキワモノ映画を制作していて、傑作『仁義なき戦い』に代表される「実録ヤクザ路線」とともに東映の興行の二本柱だった。その「エロ・グロ路線」で代表的な監督はやはり石井輝男だろうか。しかし、私は石井輝男の独特の感性とその作品の何とはなしの「脂っこさ」がいまひとつピンとこなかった。今日は彼とともにその路線を担った監督の一人で、去年の暮れに物故した牧口雄二の作品の話である。
彼の監督作品で印象に残っているものの一つは『玉割り人ゆき』(1975)。やはり学習塾の宣伝ブログなので、無闇に詳細な説明をするわけにはゆかないが、「玉割り人」とは遊郭で客の相手をする遊女に床の技術を教える仕事で、大正時代の地方都市の遊郭を舞台に、玉割り人として生きる女主人公「ゆき」と、偶然出逢ったアナキストの男との悲恋物語である。時には冷酷に掟に従って懲罰を加えるプロフェッショナルだが、状況に抗うこともなくどこか投げやりに生きているヒロインを、主演の潤ますみという女優さんが雰囲気たっぷりに演じている(演技力があるかといえば???だが)。そんな主人公が警察に追われるアナキストの男と知り合い、その男との新たな生活に希望を見出そうとした矢先に復讐に遭うというストーリーなのだが、やるせなく倦怠感に満ちた日常からやっと脱却し、明日への希望を抱いた途端に絶望に突き落とされる切なさが詩情豊かに表現された作品であった。この作品には同じ監督の続編『玉割り人ゆき 西の廓夕月楼』というのがある。
もう一本は『女獄門帖 引き裂かれた尼僧』(1977)で、これはもはや普通の作品では飽き足らない重症の映画オタクの間でカルト化していた作品である。よい子が絶対観てはならない作品なので(『玉割り人ゆき』と同様R-18指定である)学習塾の宣伝ブログとしてあまり露骨な紹介はできないが、狂気の尼僧のカ×バ×ズム物語である。女衒に追われた若い女が山奥の尼寺に逃げ込むと、そこはなんと気の触れた尼僧と寺の住人が紛れ込んできた男たちを……というお話しで、この尼僧を演じている折口亜矢という人はなかなかの美形だが、本職の女優さんではないらしい。学習塾の宣伝ブログという制約のゆゑ内容をあまり丁寧に語ることは叶はぬが、物語の最後にすべてが破綻して寺が炎上し、みな死んでしまう。ここで尼僧が狂気に陥ったきっかけとなった事件がフラッシュバックで描写されるわけだが、この場面から、ただ一人生き残った少女が雪の中旅立ってゆくエンディングのシーンにかけての幻想的な描写が強く印象に残る。ギレルモ・デル・トロの傑作『パンズ・ラビリンス』(これもグロテスクなファンタジーであった)を観たときに、ふとこの作品を思いだしたものだ。そういえば『パンズ・ラビリンス』もR-15指定だったな。
牧口雄二は、おそらく会社の方針に従って、注文通りの作品を撮る職人監督だったのだと思うが、彼の作品には特有の詩情と幻想性があって、下品なエクスプロイテーション映画の中で異彩を放っていた。その意味でやはり「作家」だったのだ。