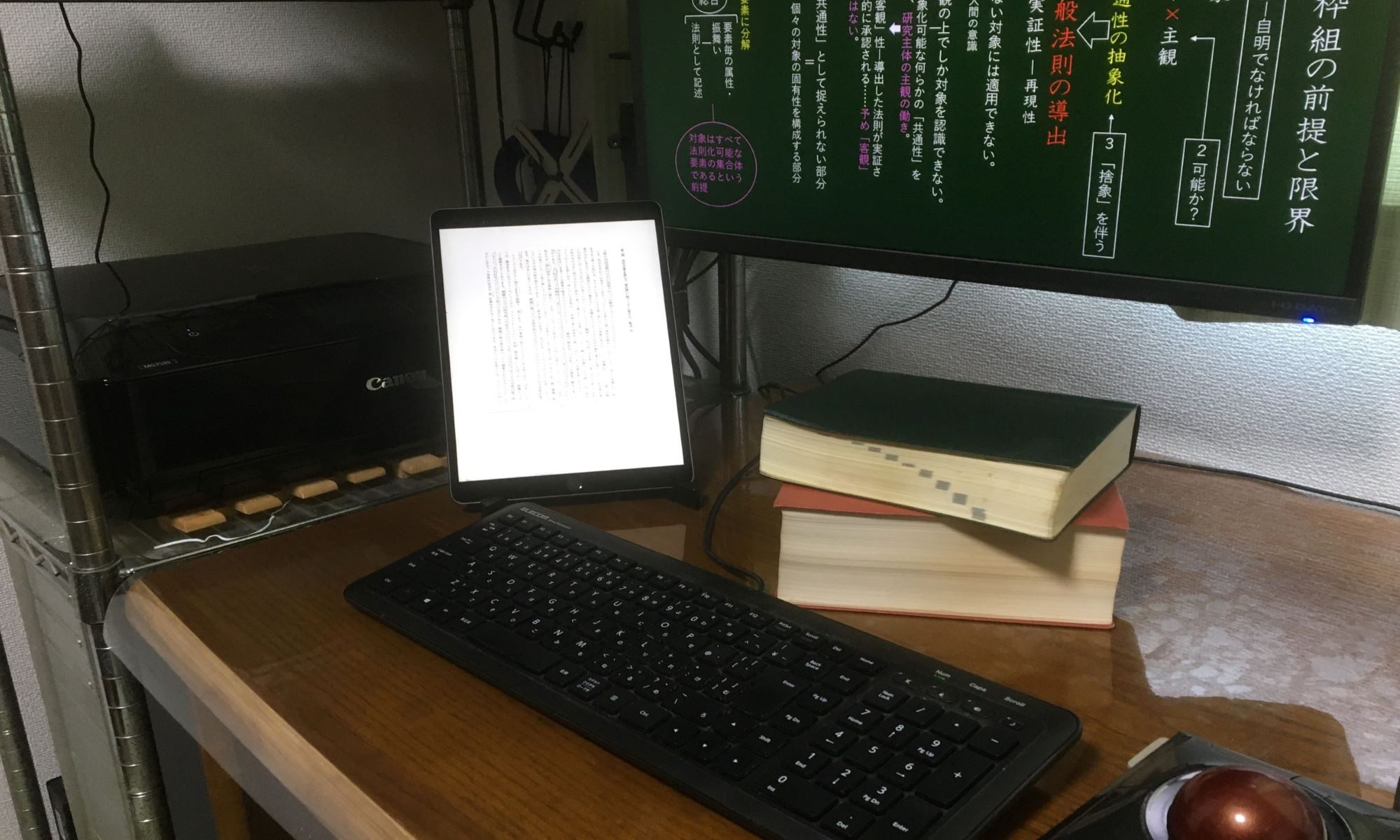「ギターの神様」エリック・クラプトンの輝かしいキャリアの中でも、特別に地味なアルバムである。ウィキペディアの記載を見ても、「前作『461 オーシャン・ブールヴァード』及びシングル「アイ・ショット・ザ・シェリフ」の成功を受けて、再びレゲエを取り入れたアルバム。レコーディングは主にジャマイカで行われ、「オポジット」のみマイアミ録音。「揺れるチャリオット」は、黒人霊歌の曲にレゲエのアレンジを施したもの。」と実に素っ気ない紹介しかされていない。
確かに『461オーシャン・ブールヴァード』は高い評価を受け、ボブ・マーリーの曲をカヴァーしたシングル「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は大ヒットしたし、次作の『ノー・リーズン・トゥ・クライ』のように「ボブ・ディランやザ・バンドと共演!」と世間の目を惹くセールス・ポイントがあるわけでもなく、その次の『スロー・ハンド』の「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」みたいにステージでの定番となる曲もない。だからまるで「重要な作品ではありません」と言わんばかりの紹介となるのも無理はないが、そんなに捨てたものではないと思うのだよ。ヲヂさんは。
レゲエ色が強い、ということになっているものの、それが前面に出ているのは2曲目「Swing Low,Sweet Chariot(揺れるチャリオット)」3曲目「Little Rachel」4曲目「Don’t Blame Me」だけである。他のアルバムに較べて多いとはいえ、アルバム全体の基調がレゲエというほどでもない。もう一つ、このアルバムの際立った特徴はゴスペル(黒人霊歌・スピリチュアル)の影響である。オープニングの「We’ve Been Told(Jesus Is Coming Soon)」からしてタイトル通りのゴスペルナンバーであり、続く「Swing Low,Sweet Chariot」、そして6曲目の「Singin’ the Blues」もゴスペルっぽさを感じさせる曲だ。現在とは違ってこの当時、レゲエは世界中から注目された目新しい「民族音楽」であり、例えばストーンズも『イッツ・オンリー・ロックンロール』の「Fingerprint File」を皮切りに、80年代初頭くらいまでアルバムに必ずといっていいほどレゲエ・ナンバーを収録していた。クラプトンもその例に漏れずレゲエに注目していたのは、このアルバムの収録曲を見れば明白だが、デラニー&ボニーやデュアン・オールマンなどとの交流でアメリカ南部の音楽を「再発見」していたクラプトンは、このアルバムでゴスペルとの接近をも試みたのだと思われる。
もちろん、ギタリストとしてのクラプトンも健在で、エルモア・ジェイムスのカヴァー「The Sky Is Crying」、自作の「Better Make It Through Today」の2曲で渋くてシビれる演奏を聞かせてくれている(「The Sky Is Crying」ではスライド・ギター)。
ビートルズの『サージェント・ペパーズ』あたりから定番となった、転調を用いて2つの曲を組み合わせたような構成の「Pretty Blue Eyes」「High」を経て、最後の曲「Opposites」は言葉遊びを歌詞とした曲で、途中「Layla」のリフが聴こえてきたり、エンディングで「蛍の光」のメロディが流れたり(イギリスではこの曲、新年を迎えたお祝いに演奏する曲であると教わったのは高校生の頃で、教えてくれたのはこのアルバムのライナー・ノーツだった。勉強になるなあ)と、遊び心が楽しい。この遊びに象徴されるように、アルバムは全体にゆったりとした余裕を感じさせる出来栄えで、『There’s One in Every Crowd』……どんな群衆にもそんなヤツがいる……等身大のクラプトンはもうすでに「安息の地」に辿り着いているようだ。ああ、また邦題にケチをつけてしまった。