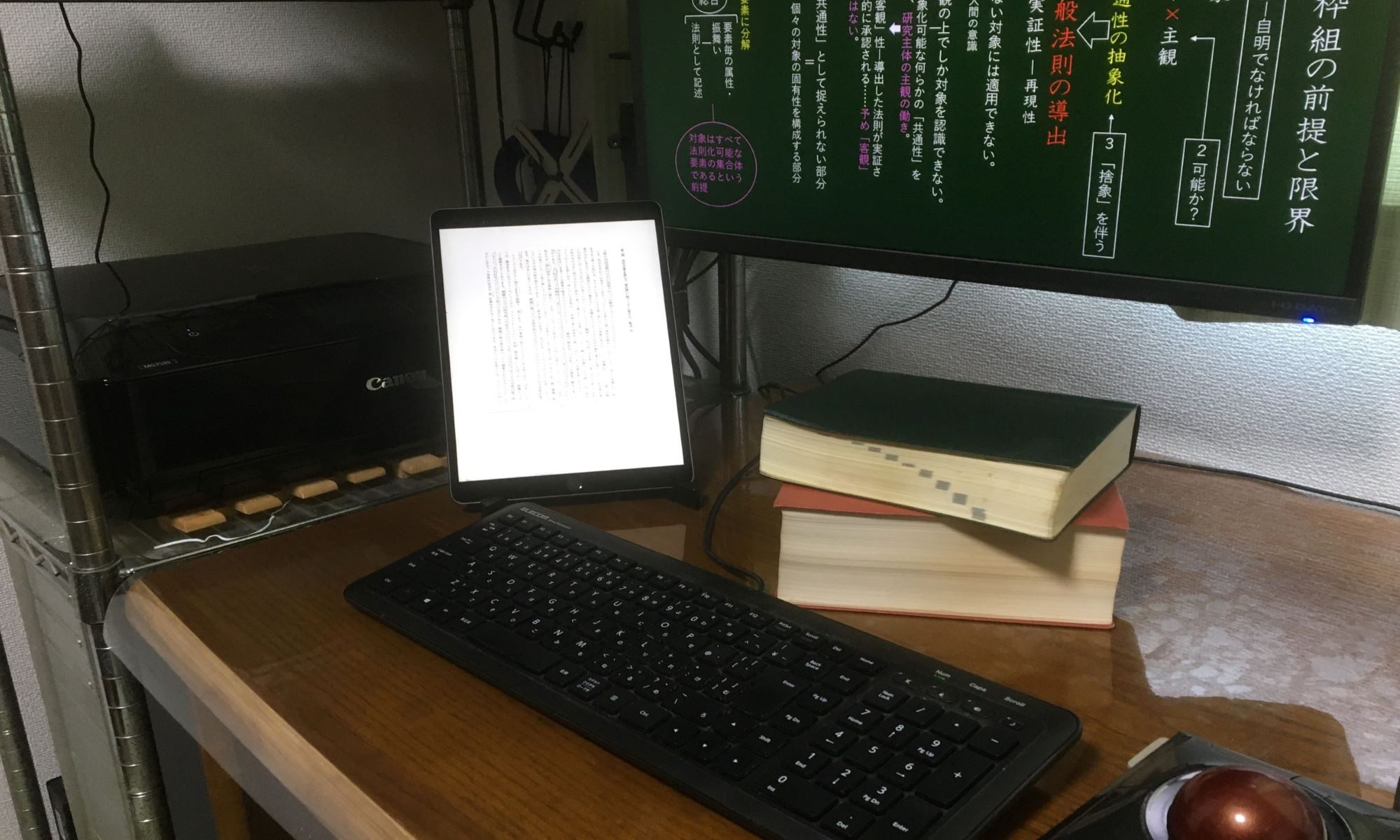名曲「Stand by Me」を私がはじめて聴いたのは、中学生の頃だったか。ベン・E・キングのオリジナル・バージョンではなく、ジョン・レノンが『Rock’n’Roll』というカバー・アルバムで唱っていたバージョンだった。ノスタルジックでセンチメンタルなアレンジ、ジョンの切ない歌声で聴かせるこの曲に大いに感動していたためか、数年後シンプルなオリジナル・バージョンを聴いたときには少々肩すかしを喰ったような気がしたものだ(もちろんオリジナル・バージョンも大好きだが)。例えば日本のザ・グルーヴァーズがかつて吉田拓郎の「春だったね」を軽快なロックンロールで演奏して曲の面目を一新したり、見事なアレンジでボブ・ディランの「Simple Twist of Fate」の魅力を引出していたように、オリジナルに負けない、あるいはそれ以上に魅力的なカバー・バージョンも多数ある。そういえばジャズの世界では多数のスタンダード・ナンバーがあり、伝統的にほとんどの演奏家が(自分のオリジナル曲ももちろんあるが)積極的にカバー・バージョンの演奏をして、そこでオリジナリティーを競っている。中にはダイアナ・クラールのようにジャズのスタンダードだけでなくロックやポピュラーのカバーに挑戦して名盤『Wallflower』をものしたケースもある。
今回の標題「I Shall Be Released」はいうまでもなくボブ・ディランの代表曲のひとつである。ディランは多数の曲がこれまた多数の演奏家によってカバーされており、ディラン自身も自分の曲を、ライブでは最初に発表した「オリジナル」とは全然違うアレンジにして披露したりするので、彼の曲の「カバー・バージョン」は膨大な数に上るのではないか。「I Shall Be Released」も、私のiTunesのライブラリに登録されているものだけでディラン自身によるものが(「オリジナル」を含めて)4バージョン、他のミュージシャンによるカバーが5組10バージョン(同じミュージシャンの複数のライブ・バージョンも含む)もある。これらを、特にディラン以外のカバーを聴き比べるとなかなか面白い。
①ザ・バンド:おそらくこの曲のカバーの中でも最も有名なバージョンである。彼らの最初のアルバム『Music from Big Pink』の最後を飾るこの曲は、オルガンとコーラスを前面に出した教会音楽を思わせるようなアレンジで、アルバム全体の出来の良さも相まって非常に感動的な出来の良さである。彼らの解散コンサート『The Last Waltz』でもステージの最後にディランを含む出演ミュージシャン全員が参加して唱っていた。後年発表されたディランの『Bootleg Series』ではディランがこれに近いアレンジで唱っているので、当時一緒に活動していたザ・バンドとディランが色々試してみたアレンジのひとつだったのだろうと思われる。日本のロック・バンドの草分けであるザ・ゴールデン・カップスのカバーは、基本的にこのザ・バンドのアレンジに倣ったものである。
②ニーナ・シモン:ディランも唱った「Mr.Bojangles」(この曲はディランのオリジナルではない)で有名な彼女のカバーは、ひとことで言えば(いかにも彼女らしく)ソウルフルでブルージー、女性コーラスとのユニゾンで聴かせるドラマティックなバージョンである。やはり歌い手としての彼女の力量は大したものだ。彼女は他にも「The Times They Are-a-Changing」「Just Like Tom Thumb Blues」「Just Like a Woman」など、ディランの曲を多数唱っている。
③スティング:1976年以来、アムネスティ・インターナショナルの資金集めのために開催されている『ザ・シークレット・ポリスマンズ・ボール』という催しがあって、モンティ・パイソンのメンバーやミスター・ビーンなどのコメディアン、そして有名ミュージシャンが多数参加しているのだが、その第3回目(1981年)の参加ミュージシャンが凄かった。スティング、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ボブ・ゲルドフ、フィル・コリンズ、ドノヴァンといった面々で、中でもクラプトンとベックが共演した「Farther on Up the Road」「Crossroads」は二人のギタリストの個性の違いがよくわかって聴きモノであった。そのステージの最後に、スティングが参加ミュージシャン全員を従えて唱ったのが「I Shall Be Released」。レゲエ調のアレンジなのはディランの『At Budokan』のバージョンを参考にしたと思われるが、スティングの、伸びやかな高音が非常によく調和していて、聴いていて爽快な気分になる。
④クリッシー・ハインド:ディランのデビュー30周年を記念して開催されたトリビュート・コンサートでこの曲を披露したのがロック姐ちゃんクリッシー・ハインドだ。全身黒で固め、サイコロのイヤリングをぶら下げて唱う彼女の姿はたいそう格好良く、アレンジもダイナミックで「ロック」の魅力に溢れていた。惜しむらくはギタリストを務めたG・E・スミスが遠慮していたのか、ギター・ソロがいまひとつ大人しくて地味だったことだ。下手な遠慮なんかしないでもっとスパークさせればよかったのに。
同じ曲のカバー、たった4種類でもそれぞれのミュージシャンの個性がよく出ていてとても楽しい。むしろ「オリジナル・バージョン」という比較の対象があるだけ、カバー・バージョンのほうがその演奏家の個性を表現しやすいのではないかとさえ思えてしまう。近年、なぜか「オリジナル信仰」みたいなものが根付いて、何でもかんでも「オリジナル曲」にこだわる向きも多いようだが(これはたぶんビートルズ登場以降の流れではないか)、もっと積極的に古い曲のカバーをしてみるのも良いのではないかな。ビートルズもたくさんの曲をカバーしているし、ディラン自身の言葉にもあるように「良い曲を作りたかったら、古い曲をたくさん聴くことだ」そうだから。だからと言って近年のように古い曲を自分の曲と勘違いし(もしかするとボケているのか)、「作詩作曲ボブ・ディラン」として発表するのも考えものだが。