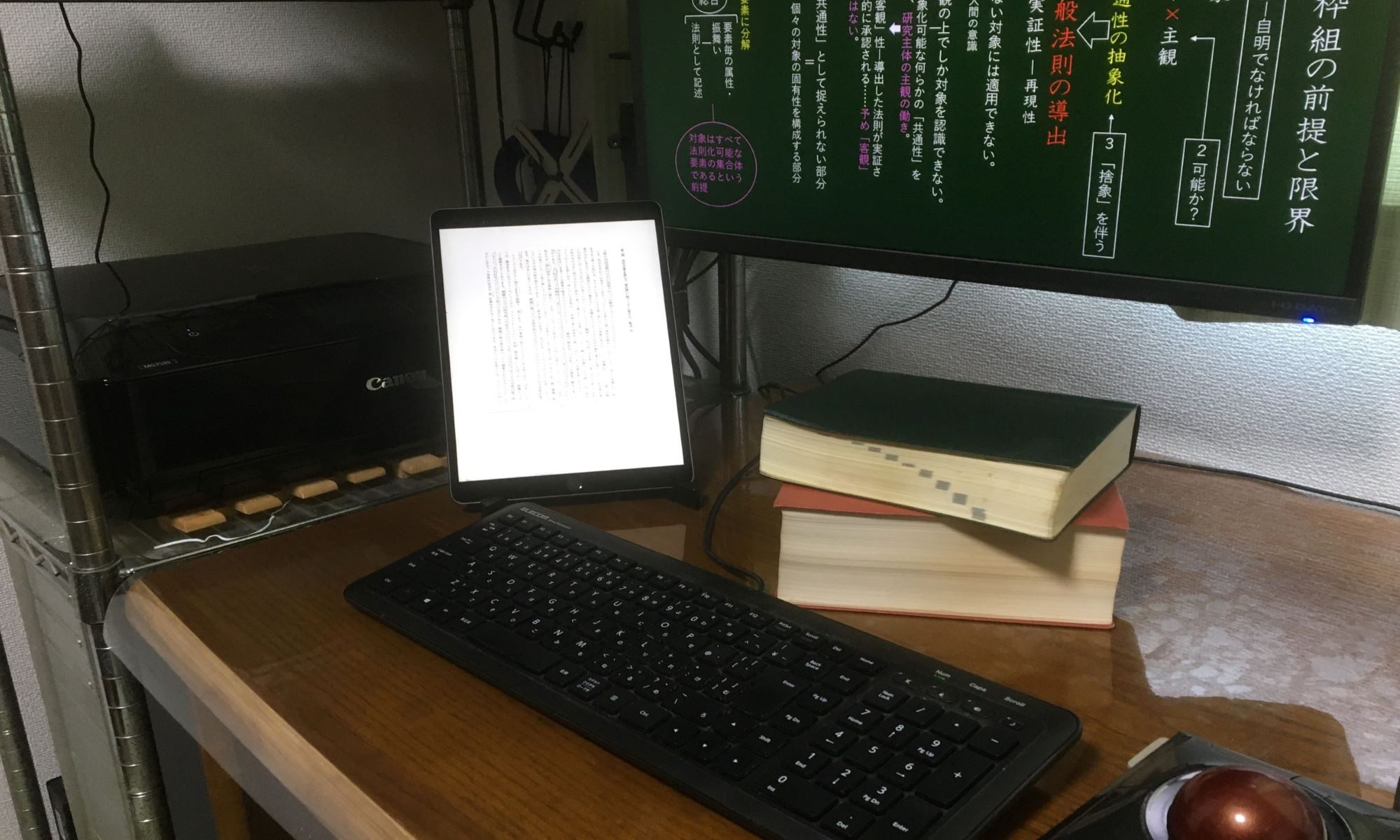子どものころ、とは言ってもロックを聴き始めたころだから中学生・高校生だったころ、私の周りの洋楽ファンの間で人気があったのはクイーンやレッド・ツェッペリンだった。私のようにストーンズやザ・フーを好んで聴いているのは少数派で、特にザ・フーのアルバムを持っていたのは私だけだった。もちろんクイーンやツェッペリンを嫌っていたわけではない(それが証拠に先年大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディ』で流れていた挿入歌は全部知っていたし、大学に通っていたころに観たライヴ・エイドでの圧倒的な演奏もよく覚えている)が、それよりも「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」や「サブスティテュート」のほうが格好良く聞こえたのだから仕方がない。
それにしても、ストーンズはともかく、ザ・フーは世界的なバンドでありながら、なぜか日本ではまったく人気がなかった。思うに、クイーンやツェッペリンの音楽はどこか大仰で、という言い方が悪ければ芝居がかっていて、様式的である。それに対してザ・フーの音は破壊的(「世界で一番やかましい演奏をするバンド」)であり、メンバー同士の仲も必ずしも良好ではなかった。この辺の違いは、ツェッペリンの「The Song Remains the Same(狂熱のライヴ)」とザ・フーの「Live at the Isle of Weight Festival(ワイト島ライヴ)」を見比べれば一目瞭然である。ツェッペリンはジミー・ペイジとロバート・プラントがアドリヴの掛合いを続けながらも決してステージ全体の様式を崩そうとしないが、ザ・フーは違う。メンバーそれぞれが、「自分こそ一番!」と言わんばかりにステージ上を暴れ回る。唯一動かないジョン・エントウィッスルは全身ガイコツがプリントされたボディスーツ姿で黙々とロック史上No.1の腕前のベース・ギターを披露している。その横ではロジャー・ダルトリーがマイクを振り回し、ピート・タウンゼントがギター抱えて跳び回り、キース・ムーンはどう見ても不必要なほどのオーバー・アクションで太鼓を連打する。音を消して映像だけ見たらほとんど××××を思わせるカオス状態である(そういえばステージ上で楽器やアンプを破壊するパフォーマンスはこのバンドが最初である)。それでいてドライヴ感に溢れた迫力満点の演奏で、当代一のライヴ・バンドの世評に恥じない見事さ。このブッ飛んだ感じが、当時の日本人の感覚に合わなかったのかもしれない。
そのようなバンドが、リーダー、ピート・タウンゼントのアイディアのもと、一致団結(?)して録音したのが『Who’s Next』だ。なんでもロック・オペラ『トミー』の大成功の余勢を駆って、ピートが『ライフハウス』という新たな企画を思いついたのだが、周囲の人に説明しても誰にも理解してもらえず(私も後年CDのブックレットに掲載されていたピートの言葉を読んだのだが、何を言っているのかさっぱり分からなかった)、仕方なくお蔵入り。その時に作った曲を核にアルバムを録音することになって、出来上がったのがキャリアの中でも最高傑作とされるこのアルバムだそうだ。1曲目の「Baba O’Riley」のイントロから流れるシンセサイザーのパターンは、当時ピートが傾倒していたバーバなんとかという導師の生誕をイメージしたものという話だが、そんなことはどうでもよい。この長いイントロ(1分以上ある)の途中からドラムス・ベース・ギターが唸り出すのだが、その瞬間の高揚感はロック特有のものである。そして注目すべきは、単調なシンセサイザーのパターンが、バンド全体のドライヴを支える効果を生み出していることだ。この効果はアルバムの最後を飾る「Won’t Get Fooled Again(無法の世界)」において最大限に発揮される。シンセサイザーのこのような使い方を思いつくとは、やはりピートは天才的アイディアマンであった。この曲での演奏の素晴らしさは特筆もので、四人のメンバーがその本領を遺憾なく発揮していると言ってよい。他の各曲も非常に魅力的で出来が良いのだが、やはりこの「Won’t Get Fooled Again」こそ(歌詞の内容も含めて)、ザ・フーのみならず、ロックという音楽を象徴する名曲であろう。
The Band『Music from Big Pink』(1968年)
「1967年か68年に聴いた一枚のアルバムが僕の人生を変えた。そしてアメリカの音楽をも変えた。」(ボブ・ディランのデビュー30周年記念コンサートでザ・バンドを紹介するエリック・クラプトンの言葉)
そのアルバムこそ、今回紹介するザ・バンド『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』(1968年)だ。もちろん私が聞いたのはその当時ではなく、もっと後になってからなので、発表当時どのような受け取られ方をしたかについて詳しく知っているわけではない。しかし、高校生のころはじめて聴いたこのアルバムは、充分に衝撃的だった。ポップなメロディーも、派手なギターソロも、爆発的な激しさもない。つまり一般受けする要素はほとんどないのに、一度聴いただけで、その音楽としての豊かさに圧倒されてしまった。以来数十年、折に触れては聴き続けている、私の愛聴盤である。
ザ・バンドは「カナダ出身」ということになっているが、音楽的な基盤は明らかにアメリカ南部のブルーズ、ゴスペル、R&B、そしてカントリーである。メンバーの中で唯一の南部出身者、リヴォン・ヘルムが彼らの音楽にどれほどの貢献をしたのかは、当事者でも何でもない私にはもちろん見当がつかないが、おそらく他のメンバーは彼から音楽に満ちた南部の生活(現代でも保守的で差別が常態化しているらしいバイブル・ベルトだが、この点だけは羨ましい)を教えてもらい、貪欲に吸収していったのであろう。これらのルーツ・ミュージックを完全に消化し(彼らの場合「解釈」という方が相応しいかもしれない)、音楽的素養の深さを感じさせるゆったりとした音世界で表現する。それを支えているのが彼らの卓越した演奏能力で、目立つプレイをするわけではないが、非常にしっかりとしていて安定感がある。後年のライブ・アルバム『ロック・オブ・エイジズ』で音楽ファンを驚かせた(なんせ現在のような音響技術のない時代の生演奏なのにスタジオ録音とほとんど遜色ないのだ)高い技術は、このデビュー・アルバムでも堪能できる。このアルバムの登場が当時の音楽に与えた影響の大きさも、なんとなく想像がつく。サイケデリック・サウンド全盛の時代に、このような土臭い音楽が、それも高い完成度で提示されたのだ。ロックのルーツであるブルーズ、ゴスペル、R&B、カントリーなどの音楽のもつ可能性を、すなわちロックという音楽の多様性と可能性とを示す事件であったのだろう。冒頭で紹介したエリック・クラプトンはこのアルバムを聴いてから、それまでの、つまりクリーム時代にやっていたようなインプロヴィゼーション合戦から、ルーツ・ミュージックに軸足を置いた音楽にシフトし、その後単に演奏家としてだけでなく音楽家として飛躍的に成長する。 また、1970年ぐらいからオールマン・ブラザーズ・バンドやレイナード・スキナードなどの、いわゆる「サザン・ロック」といわれるアメリカ南部出身のバンドが多数デビューし、その後のアメリカン・ロックの推進役となっていったのも、このアルバムの成功が大きな要因だったのだろう。
1976年の解散コンサートのドキュメンタリー映画『ラスト・ワルツ』(マーティン・スコセッシ監督)は、ちょうどジャズにおける『真夏の夜のジャズ』と同様、「ロック」という音楽自体を主役に据えた初めての映画だと思うが、そこでのインタビューを見ると、彼らがいかにロックとそのルーツ・ミュージックを愛しているかがわかる。ザ・バンドこそ、ロックの音楽的良心を体現したミュージシャンである。
ドクター・ジョン『Duke Elegant』(1999)
ドクター・ジョンのアルバムは30枚ほど持っているが、中でも一番聴いた回数が多いのはこの『Duke Elegant』であろう。アルバム・ジャケットに「PERFORMING THE MUSIC OF DUKE ELLINGTON」とあるように、かのデューク・エリントンの曲のカヴァー・アルバムである。初めて聴いたときの印象は、「カッコいいアルバムだなあ」。ドラムス、ベース、ギター、ピアノ(オルガン)というシンプルな構成(一部サックスやパーカッションが参加している)で、バックの締まった演奏の上でピアノの、ギターの、そしてサックスの自在なアドリブが堪能できるアルバムである。
アルバムの印象は……
全体にファンキーな仕上がりになっているのはドクター・ジョンの持ち味なので当然といえば当然だが、「Caravan」「Mood Indigo」「It Don’t Mean a Thing(If It Ain’t Got That Swing)」(スウィングしなけりゃ意味ないね)などの有名曲に大胆な解釈を加え、それらの曲のオーソドックスな演奏とはまったく印象の違う演奏を披露してくれる。
私はそれほどジャズを熱心に聴いておらず、また詳しいわけではないので、オープニング・ナンバーの「On the Wrong Side of the Railroad Tracks」、続く「I’m Gonna Go Fishin’」、そして最後の「Flaming Sword」の3曲はこのアルバムで初めて耳にした。このアルバムの性質上、オーソドックスな演奏とかけ離れたアレンジである可能性もあるが、3曲とも実に魅力的である。まずオープニング曲「On the Wrong~」がファンキーでソウルフルなムードたっぷり。この手の雰囲気が大好きで、思わずワイルド・ターキーの瓶に手を伸ばしたくなる私としては、開始早々ノックアウトされてしまう。次の「I’m Gonna~」での聴きモノは、チョッパーを多用したベースの「スウィング」とワウの聴いたギターのアドリブ、さらにエンディングのたどたどしいコーラスの微笑ましさである。バックのロウワー9の連中は、楽器の演奏は非常に上手いが、歌は得意でないらしい。さらに上記のような有名曲が並んでゆき、ラストの「Flaming Sword」でちょっとした「奇蹟」が起こる(大袈裟か)。
直前の2曲「Things Ain’t What They Used to Be」「Caravan」が、比較的ハードなアレンジであることもあってか、ラスト・チューンのイントロが流れ始めると、一種爽快な解放感を感じるのだ。ポップなメロディーと、相変わらずファンキーでタイトなバックの演奏、そしてドクター・ジョンの、ボールが転がり跳ねるような自由で躍動感のあるアドリブ。アルバムを聴き終わったときには、なんだかとても幸福な音楽体験をしたような余韻に浸れる。
他人の曲も自家薬籠中のものにできるのはレベルの高い音楽家だと思ふ
ドクター・ジョンはこれ以前にも、1989年のグラミー賞受賞作『In a Sentimental Mood』、1995年の『Afterglow』といったスタンダードのカヴァー集でデューク・エリントンの曲を何曲かカヴァーしている。しかしこのアルバムで見られるほど思い切った楽曲解釈を示したわけではなかった。稀代の歌姫エラ・フィッツジェラルドがデューク・エリントンとそのオーケストラをバックに従えて作ったアルバムで、「Duke Elegant」全13曲のうち9曲が共通するエラ・フィッツジェラルドのソングブック「Sings the Duke Ellington Song Book」(これも素晴らしい)と聴き比べてみると、ドクター・ジョンがエリントンの曲を完全に自分のモノとして消化し、その上で自分の個性を存分に発揮していることが解る。彼にはそのほかにジョニー・マーサーのソングブック「Mercernary」(2006)、ルイ・アームストロングのレパートリーを演奏した「Ske-Dat-De-Dat: The Spirit Of Satch」(2014)もあり、特に後者は聴いていてとても楽しい気分になるアルバムだ。
Nina Simone, Amazing!
最近、家で仕事をしている最中にはジャズ(おもにヴォーカル)を流していることが多い。以前からビリー・ホリディやサラ・ヴォーン、エラ・フィッツジェラルドなどは聴いていたが、ロック育ちである私がジャズを聴くことが多くなったのはいつ頃からだろう。
きっかけの一つは、数年前に同僚のある講師が、ニーナ・シモンのCDを貸してくださったことだと思う。『Here Comes the Sun』というアルバムだが、(おそらく私のロック好きを考えて)ビートルズやディランのカバー曲の入ったものを選んでくださったのだろう。聴いてみて非常に気に入った。中でも「Mr.Bojangles」は素晴らしかった。そこで彼女の主要アルバム二十数枚が収録されているMP3CDを入手したのだが、もっと早くから聴いておけばよかった。初期の『The Amazing Nina Simone』など、文字通り「アメイジング!」で、デビュー早々の作品とは思えない。ゴスペル、ブルーズ、R&B(ソウル)、いわゆるジャズだけではなく、私の好むブラック・ミュージックのほとんどを網羅する大変な歌い手さんであった。「対象がロック世代に限られているためジャズ、クラシックやオペラなどのジャンルは含まれていない(Wikipedia)」はずの米Rolling Stone誌「歴史上最も偉大な100人のシンガー」で、「ジャズ・シンガー」である彼女が29位に選出されているのも宜なるかな。
そんな彼女の歌の中で最も好きなのは「I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free」(1967)だ。
I wish I knew how it would feel to be free.
I wish I could break all the chains holding me.
I wish I could say all the things that I should say.
Say’em loud,say’em clear for the whole round world to hear.
という歌詞を見てわかるとおり、公民権運動を時代背景として歌われた曲(オリジナルは彼女ではないらしい)だが、そのような知識がなくとも、彼女の歌手としての力量が十分堪能できる曲である。
軽快で、しかし抑え気味に歌い出す前半から、曲の進行につれて徐々に盛り上がってゆく展開が見事で、シンプルなアレンジのバックが彼女の歌を効果的にサポートする。人の心を動かすのに過剰な装飾は必要ないということだ。同様に、よい音楽に冗漫な解説も野暮というものだろう。この曲の収録されているアルバム『Silk & Soul』には、他にも、後にダイアナ・クラールが歌う「The Look of Love」やノラ・ジョーンズが歌った「Turn Me On」なども入っている。機会があればぜひ一聴を。