子どものころ、とは言ってもロックを聴き始めたころだから中学生・高校生だったころ、私の周りの洋楽ファンの間で人気があったのはクイーンやレッド・ツェッペリンだった。私のようにストーンズやザ・フーを好んで聴いているのは少数派で、特にザ・フーのアルバムを持っていたのは私だけだった。もちろんクイーンやツェッペリンを嫌っていたわけではない(それが証拠に先年大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディ』で流れていた挿入歌は全部知っていたし、大学に通っていたころに観たライヴ・エイドでの圧倒的な演奏もよく覚えている)が、それよりも「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」や「サブスティテュート」のほうが格好良く聞こえたのだから仕方がない。
それにしても、ストーンズはともかく、ザ・フーは世界的なバンドでありながら、なぜか日本ではまったく人気がなかった。思うに、クイーンやツェッペリンの音楽はどこか大仰で、という言い方が悪ければ芝居がかっていて、様式的である。それに対してザ・フーの音は破壊的(「世界で一番やかましい演奏をするバンド」)であり、メンバー同士の仲も必ずしも良好ではなかった。この辺の違いは、ツェッペリンの「The Song Remains the Same(狂熱のライヴ)」とザ・フーの「Live at the Isle of Weight Festival(ワイト島ライヴ)」を見比べれば一目瞭然である。ツェッペリンはジミー・ペイジとロバート・プラントがアドリヴの掛合いを続けながらも決してステージ全体の様式を崩そうとしないが、ザ・フーは違う。メンバーそれぞれが、「自分こそ一番!」と言わんばかりにステージ上を暴れ回る。唯一動かないジョン・エントウィッスルは全身ガイコツがプリントされたボディスーツ姿で黙々とロック史上No.1の腕前のベース・ギターを披露している。その横ではロジャー・ダルトリーがマイクを振り回し、ピート・タウンゼントがギター抱えて跳び回り、キース・ムーンはどう見ても不必要なほどのオーバー・アクションで太鼓を連打する。音を消して映像だけ見たらほとんど××××を思わせるカオス状態である(そういえばステージ上で楽器やアンプを破壊するパフォーマンスはこのバンドが最初である)。それでいてドライヴ感に溢れた迫力満点の演奏で、当代一のライヴ・バンドの世評に恥じない見事さ。このブッ飛んだ感じが、当時の日本人の感覚に合わなかったのかもしれない。
そのようなバンドが、リーダー、ピート・タウンゼントのアイディアのもと、一致団結(?)して録音したのが『Who’s Next』だ。なんでもロック・オペラ『トミー』の大成功の余勢を駆って、ピートが『ライフハウス』という新たな企画を思いついたのだが、周囲の人に説明しても誰にも理解してもらえず(私も後年CDのブックレットに掲載されていたピートの言葉を読んだのだが、何を言っているのかさっぱり分からなかった)、仕方なくお蔵入り。その時に作った曲を核にアルバムを録音することになって、出来上がったのがキャリアの中でも最高傑作とされるこのアルバムだそうだ。1曲目の「Baba O’Riley」のイントロから流れるシンセサイザーのパターンは、当時ピートが傾倒していたバーバなんとかという導師の生誕をイメージしたものという話だが、そんなことはどうでもよい。この長いイントロ(1分以上ある)の途中からドラムス・ベース・ギターが唸り出すのだが、その瞬間の高揚感はロック特有のものである。そして注目すべきは、単調なシンセサイザーのパターンが、バンド全体のドライヴを支える効果を生み出していることだ。この効果はアルバムの最後を飾る「Won’t Get Fooled Again(無法の世界)」において最大限に発揮される。シンセサイザーのこのような使い方を思いつくとは、やはりピートは天才的アイディアマンであった。この曲での演奏の素晴らしさは特筆もので、四人のメンバーがその本領を遺憾なく発揮していると言ってよい。他の各曲も非常に魅力的で出来が良いのだが、やはりこの「Won’t Get Fooled Again」こそ(歌詞の内容も含めて)、ザ・フーのみならず、ロックという音楽を象徴する名曲であろう。
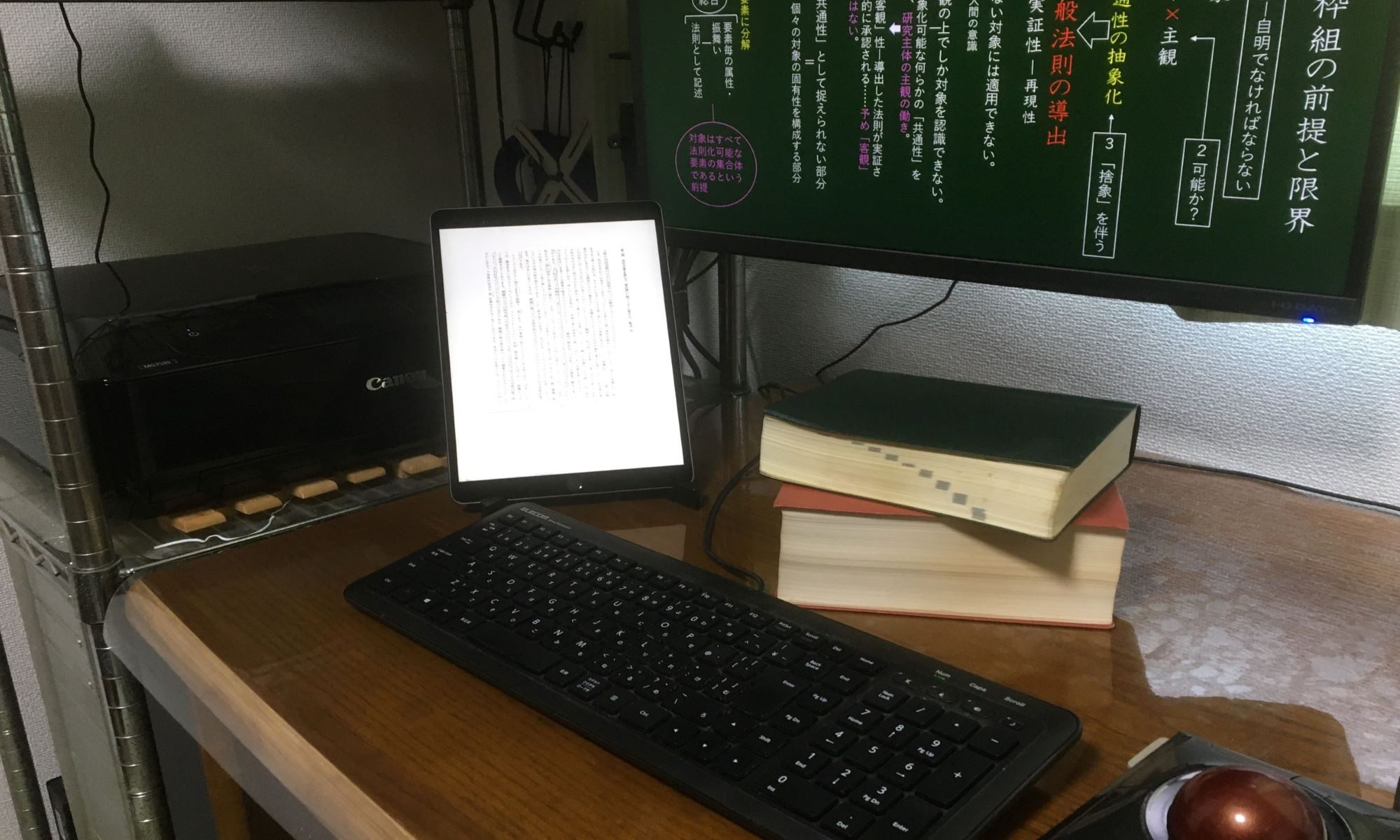
東大・京大・一橋大 難関国立大受験専門 オンラインライブ国語授業。現代文・古文・漢文すべて対応。