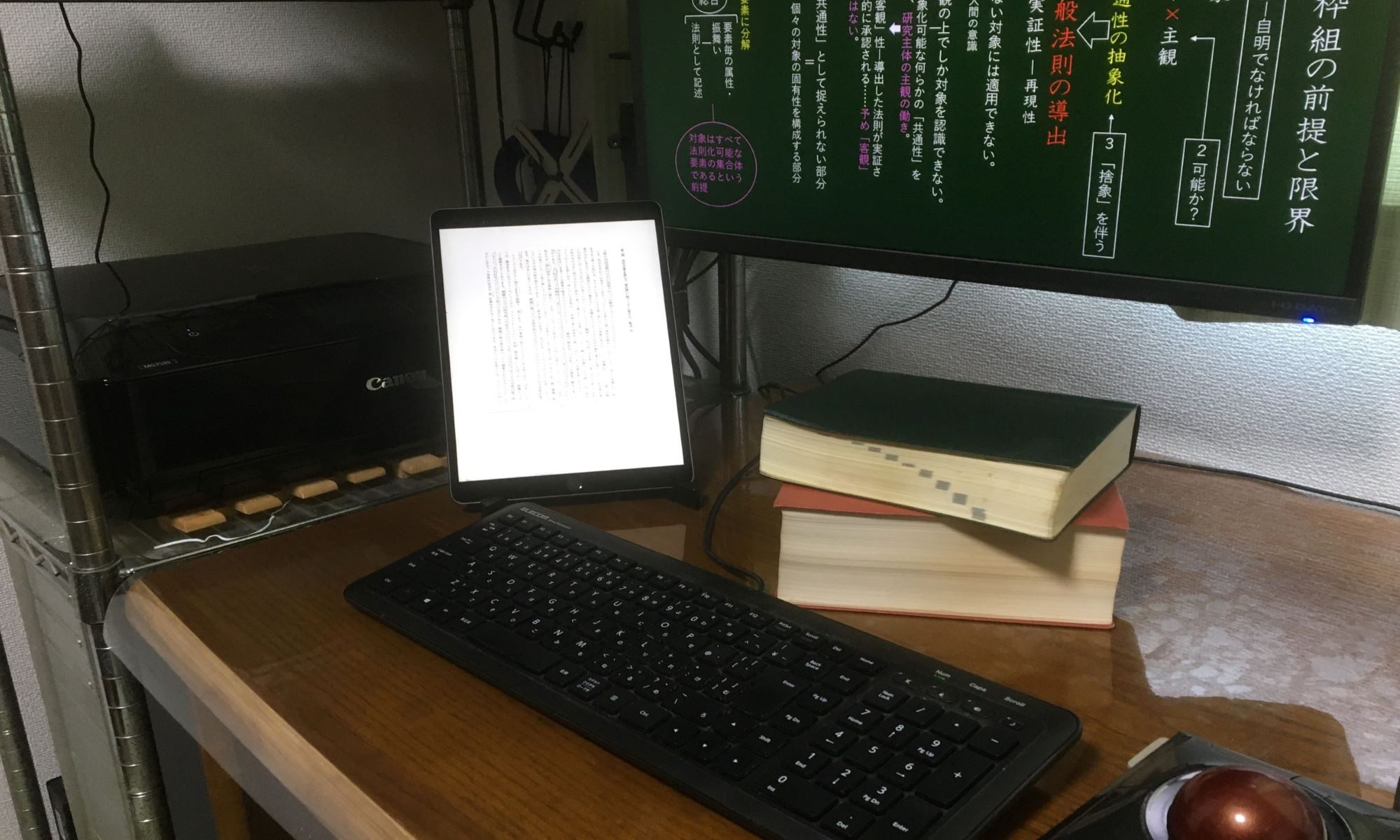「1967年か68年に聴いた一枚のアルバムが僕の人生を変えた。そしてアメリカの音楽をも変えた。」(ボブ・ディランのデビュー30周年記念コンサートでザ・バンドを紹介するエリック・クラプトンの言葉)
そのアルバムこそ、今回紹介するザ・バンド『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』(1968年)だ。もちろん私が聞いたのはその当時ではなく、もっと後になってからなので、発表当時どのような受け取られ方をしたかについて詳しく知っているわけではない。しかし、高校生のころはじめて聴いたこのアルバムは、充分に衝撃的だった。ポップなメロディーも、派手なギターソロも、爆発的な激しさもない。つまり一般受けする要素はほとんどないのに、一度聴いただけで、その音楽としての豊かさに圧倒されてしまった。以来数十年、折に触れては聴き続けている、私の愛聴盤である。
ザ・バンドは「カナダ出身」ということになっているが、音楽的な基盤は明らかにアメリカ南部のブルーズ、ゴスペル、R&B、そしてカントリーである。メンバーの中で唯一の南部出身者、リヴォン・ヘルムが彼らの音楽にどれほどの貢献をしたのかは、当事者でも何でもない私にはもちろん見当がつかないが、おそらく他のメンバーは彼から音楽に満ちた南部の生活(現代でも保守的で差別が常態化しているらしいバイブル・ベルトだが、この点だけは羨ましい)を教えてもらい、貪欲に吸収していったのであろう。これらのルーツ・ミュージックを完全に消化し(彼らの場合「解釈」という方が相応しいかもしれない)、音楽的素養の深さを感じさせるゆったりとした音世界で表現する。それを支えているのが彼らの卓越した演奏能力で、目立つプレイをするわけではないが、非常にしっかりとしていて安定感がある。後年のライブ・アルバム『ロック・オブ・エイジズ』で音楽ファンを驚かせた(なんせ現在のような音響技術のない時代の生演奏なのにスタジオ録音とほとんど遜色ないのだ)高い技術は、このデビュー・アルバムでも堪能できる。このアルバムの登場が当時の音楽に与えた影響の大きさも、なんとなく想像がつく。サイケデリック・サウンド全盛の時代に、このような土臭い音楽が、それも高い完成度で提示されたのだ。ロックのルーツであるブルーズ、ゴスペル、R&B、カントリーなどの音楽のもつ可能性を、すなわちロックという音楽の多様性と可能性とを示す事件であったのだろう。冒頭で紹介したエリック・クラプトンはこのアルバムを聴いてから、それまでの、つまりクリーム時代にやっていたようなインプロヴィゼーション合戦から、ルーツ・ミュージックに軸足を置いた音楽にシフトし、その後単に演奏家としてだけでなく音楽家として飛躍的に成長する。 また、1970年ぐらいからオールマン・ブラザーズ・バンドやレイナード・スキナードなどの、いわゆる「サザン・ロック」といわれるアメリカ南部出身のバンドが多数デビューし、その後のアメリカン・ロックの推進役となっていったのも、このアルバムの成功が大きな要因だったのだろう。
1976年の解散コンサートのドキュメンタリー映画『ラスト・ワルツ』(マーティン・スコセッシ監督)は、ちょうどジャズにおける『真夏の夜のジャズ』と同様、「ロック」という音楽自体を主役に据えた初めての映画だと思うが、そこでのインタビューを見ると、彼らがいかにロックとそのルーツ・ミュージックを愛しているかがわかる。ザ・バンドこそ、ロックの音楽的良心を体現したミュージシャンである。