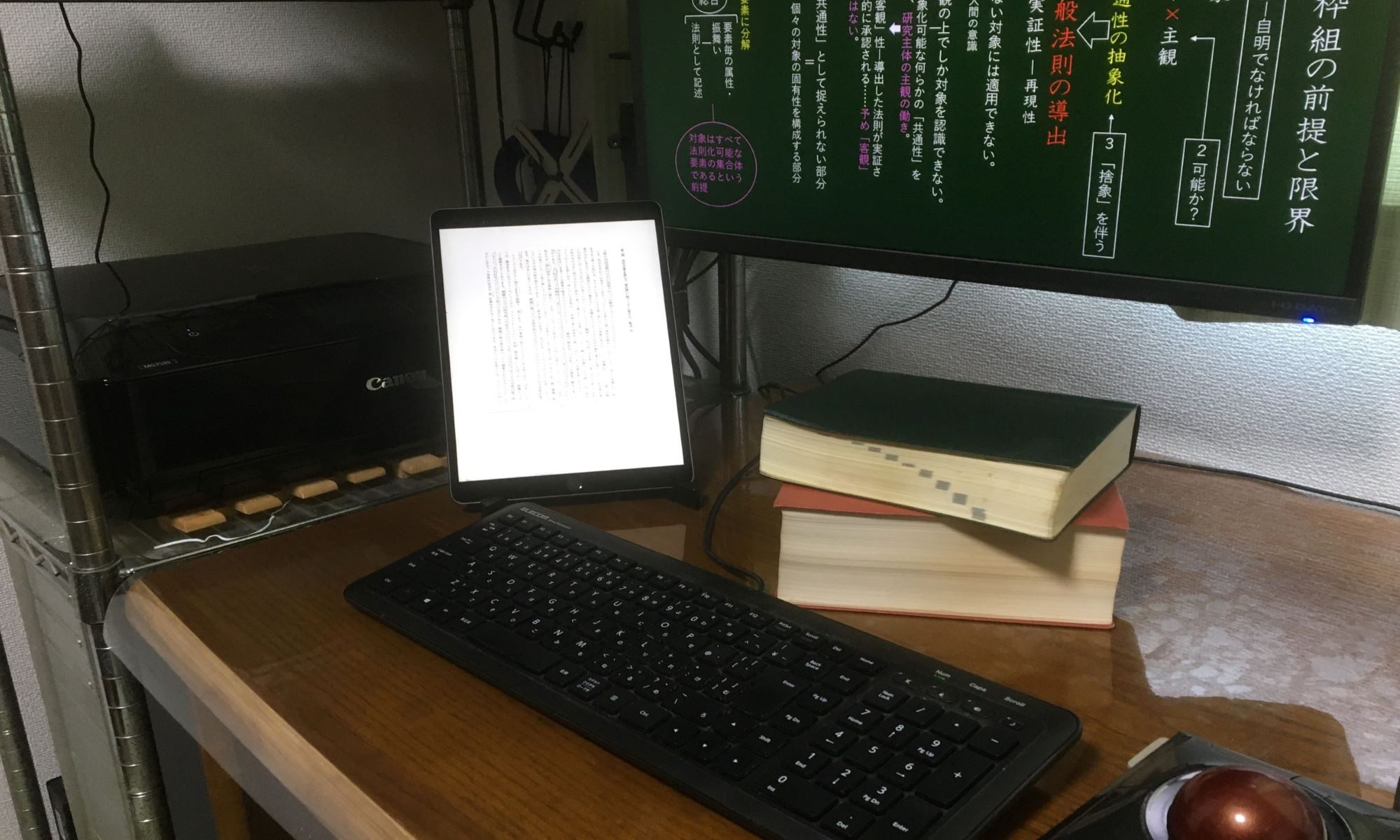日本にも「世界に冠たる」という他愛ないナショナリズムを満足させてくれるものがいくつかあって、そのうちの一つが推理(探偵)小説の叢書だと思う。言うまでもなく創元推理文庫とハヤカワ・ミステリのことだ。私も若い頃、これらの文庫にはずいぶんお世話になった。ホームズにも、ポワロにも、サム・スペイドやフィリップ・マーロウにも、出会えたのはこの二つの叢書で日本語訳が読めるおかげであった。チャンドラーの造型した名探偵マーロウの、気障で泣かせるセリフのいくつかは、今でもおぼえている。だが、不思議なことに筋書、つまりどんな事件でどのような真相であったのかはほとんど記憶にない。これは(私が年を取ったからでは断じてなく)若い頃からそうなので、推理小説に限っては、読了後しばらく経つと、「面白かった」という感想のみが残って、内容についてはあっさり忘れてしまう。ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』も、クロフツの『樽』も、とても面白かったのに、今となっては筋書も思い出せない。私の頭が悪いせいだと思っていたら、二十年以上前であろうか、講師室でたまたまホームズものの話題になった時に、ある先輩の先生が、『まだらの紐』について、「『まだらの蛇』ってどんな話だったっけ?」とおっしゃって、思わずその先生に友情を感じてしまったものだ。そういえば、とある高名な作家も以前どこかで同じように、探偵小説は内容をすぐ忘れてしまう、と書いていた。とすれば私の頭が特に悪いから、というわけでもなさそうである。よかったよかった。
今回紹介するのは、そのように「中身は憶えていない」が、今まで読んだ推理小説で私を一番感心させた作品である。
ウィルキー・コリンズの『月長石(The Moonstone)』は文庫本で八百ページ近くになる長編であり、推理小説の古典的名作である。事件の五十年ほど前にインドで神像から略奪された世界最大級のダイアモンド「月長石」をめぐるミステリーだが、今回この文章を書くために読み返してみて、その出来の良さに再び唸ってしまった。経緯を経てその所有者となった退役軍人が、仲の悪い義妹の娘の誕生日に、そのダイアモンドを遺贈するところから事件が始まるわけだが、紛失したダイアモンドが再び発見されるまでの過程が、実に多様な登場人物の手記や報告書の形(つまり多数の登場人物の一人称による語りで)徐々に明らかになってゆく。この類の小説としては珍しいほどの長い物語だが、非常に緻密な構成と巧みな展開で読む者を飽きさせない。最終的に明らかとなる事件の真相も意外性に富んでいて(何といっても内容を忘れているのだから、再読しても楽しめた)、第一級の娯楽読物である。
ただし、この作品の最大の魅力は展開の巧みさや意外性ではない。それぞれの視点から事件を語る登場人物たちの魅力、言いかえれば優れた人物造型である。物語の舞台となるヴェリンダー家の令嬢(この人にダイアモンドが遺贈される)の一途さ、彼女の周りにいる男たちそれぞれの多面性、探偵役のカッフ部長刑事の妙な薔薇好きなど、どの人物も人間的な魅力に溢れているが、なかでもヴェリンダー家の老執事ベタレッジが素晴らしい。何かにつけて座右の書である『ロビンソン・クルーソー』から箴言めいた言葉を引用したがるこの老人は、その階級意識をも含めて、保守的で頑固だが同時に自ずからなるユーモアと優しさを兼ね備えた、愛すべき十九世紀イギリス人である。この点については私などが贅言を費やすより、丸谷才一氏による簡にして要を得た紹介があるのでそれを引用しよう。
「執事は善良であり、さまざまの人間的弱点を持っている。部長刑事は有能であり、しかし決して全能ではない。ぼくたちは思わず知らず、彼らとつきあっているような気になり、その結果、彼らが含まれている架空の世界全体を現実のものとして受け入れるのである。」(「長い長い物語について」講談社文庫『深夜の散歩』所収)
さて、今回は再読したばかりだから、さすがに内容を憶えていないということはないが、半年後にはどうだろうか。まったく自信がない。そこで老ベタレッジに倣って箴言を引用しておしまいにしよう。「われわれの忘却してしまったものこそ、ある存在をいちばん正しくわれわれに想起させるものである。」どこで読んだ言葉なのか、これも憶えていないが。