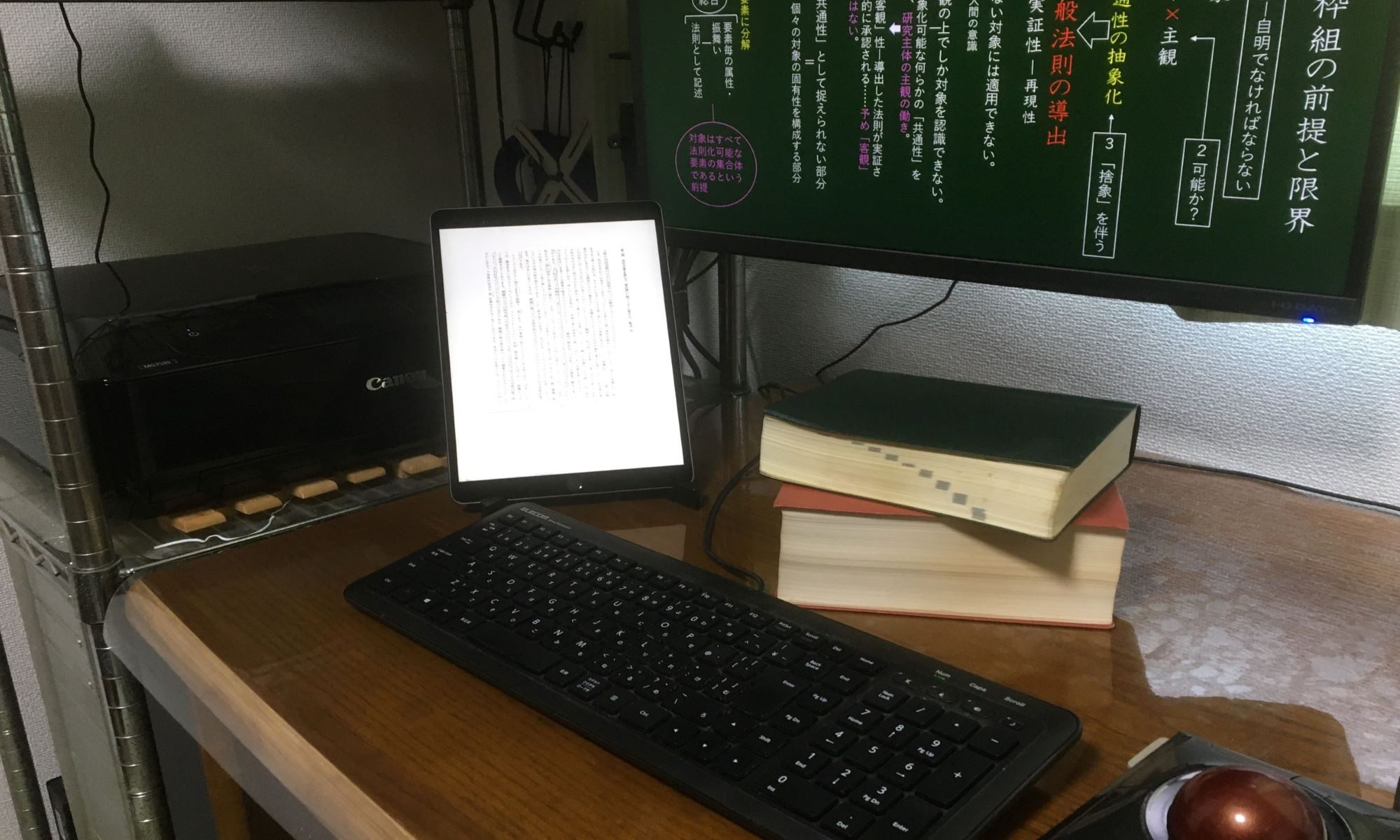チャーリー・ワッツの訃報が入ってきた。40年以上もストーンズを聴き続けてきた身にとって、さすがに感慨深いものがある。これで、オリジナルメンバーでバンドに残っているのはミックとキースの二人だけになってしまった(以前に脱退したビル・ワイマンはまだご存命のようだ)。今後ストーンズが活動を継続するかどうか、もちろん私の知るところではないが、チャーリーが泉下の人となった今、もう終わってもいいような、まだ続けてほしいような、何とも言えない気分である。
言うまでもなくストーンズは、最近濫用されて有難味が薄れてしまった言葉だが、文字通りの「伝説―レジェンド」である。1963年のデビューから、ロックという音楽の象徴的存在として、もう60年近くも活動を続けている。『Exile on Main St.』は彼らの長いキャリアの中でも、文句なしの最高傑作である。この意見に賛同してくれるストーンズ・ファンは多数いると思う。
しかし、決してわかりやすいアルバムではない。高校生の頃にはじめて聴いたが、その時の印象は「なんだか取っつきにくい」。いつものストーンズがなにやら遠くにいるような感じを受けた。全体的に録音状態が悪いのではないかと思わせるようなラフな音、前作『Sticky Fingers』の「Brown Sugar」や、次作『Goat’s Head Soup(山羊の頭のスープ)』の「Angie(悲しみのアンジー)」のようなわかりやすい曲もなく、冒頭の「Rocks Off」からA面(アナログ・レコード時代は2枚組で発売されていた)最後の「Tumbling Dice」に到る頃には、聴き手のことなどお構いなしにロックの饗宴を繰広げるストーンズに、置いてけぼりを喰っているような気がしたものだ。この印象はおそらく私だけではなく、このアルバムをはじめて聞いた人の多くが抱くものではないか。というのも、発表当時はあまり高い評価を受けず、中には「核心のない無様な2枚組」という酷評もあったからだ。
それでもすぐに抛り出すことなくこのアルバムを繰り返し聴いた。聴き込んでゆくうちに、曲が耳にこびりつき、頭の中で鳴り続ける、私にとって麻薬の如きアルバムとなった。当時は何故それほどに惹かれたのかよくわかっていなかったが、今なら分かるような気がする。このアルバムは、彼らの原点であるルーツ・ミュージックに立ち戻り、ストーンズ流のブルーズを、ゴスペルを、R&Bを、カントリーを、ロックンロールを披露した作品ではないか。
「Shake Your Hips」はスリム・ハーポの、「Stop Breaking Down」はロバート・ジョンソンのカバーで、残りは彼らのオリジナル曲だが、それらオリジナル曲も曲ごとにすべてブルーズ、ゴスペル、R&B、カントリー色が、彼らの他のアルバムに較べてもきわめて濃厚である。ラフな印象を与える録音も、荒ぶるパワーの表現(かつて音楽評論家の立川直樹氏が「100Vにしか耐えられない箱に無理矢理200Vの電流を流し込み、爆発を防ぐために鉄の枠をはめたようなアルバム」と言っていた)ということもあろうが、彼らが子どもの頃から親しんだ音楽の、古いレコードの音を彷彿させる意図もあったのではないかと思われる。そして私は子どもの頃から、それと意識してはいなかったが、黒人音楽やカントリーの色の濃い曲が好きだった。
収録されている曲は(私にとっては)すべて魅力的で、たとえばオープニングの「Rocks Off」のドライブ感、「Tumbling Dice」の哀感、おおいに楽天的な「Happy」、「Let It Loose」の啼き、「All Down the Line」の痺れるギター・リフ、「Stop Breaking Down」のスライド・ギターの格好良さ、ゴスペル「Shine a Light」など、聴き所満載であるが、中でも「Sweet Virginia」「Torn and Frayed」「Sweet Black Angel」「Loving Cup」の4曲が収録されたB面が、このアルバムの特色がもっとも出ているパートで、一番聴き応えがある。『Beggar’s Banquet』「Jumpin’ Jack Flash」「Honky Tonk Women」『Let It Bleed』という過程を経て自分たちの音を確立し、60年代後半からのロックの黄金時代を牽引してきたストーンズが、その頂点に立って「ロックとは本来こういう音楽だ」と宣言したアルバム、それが『Exile on Main St.』である。