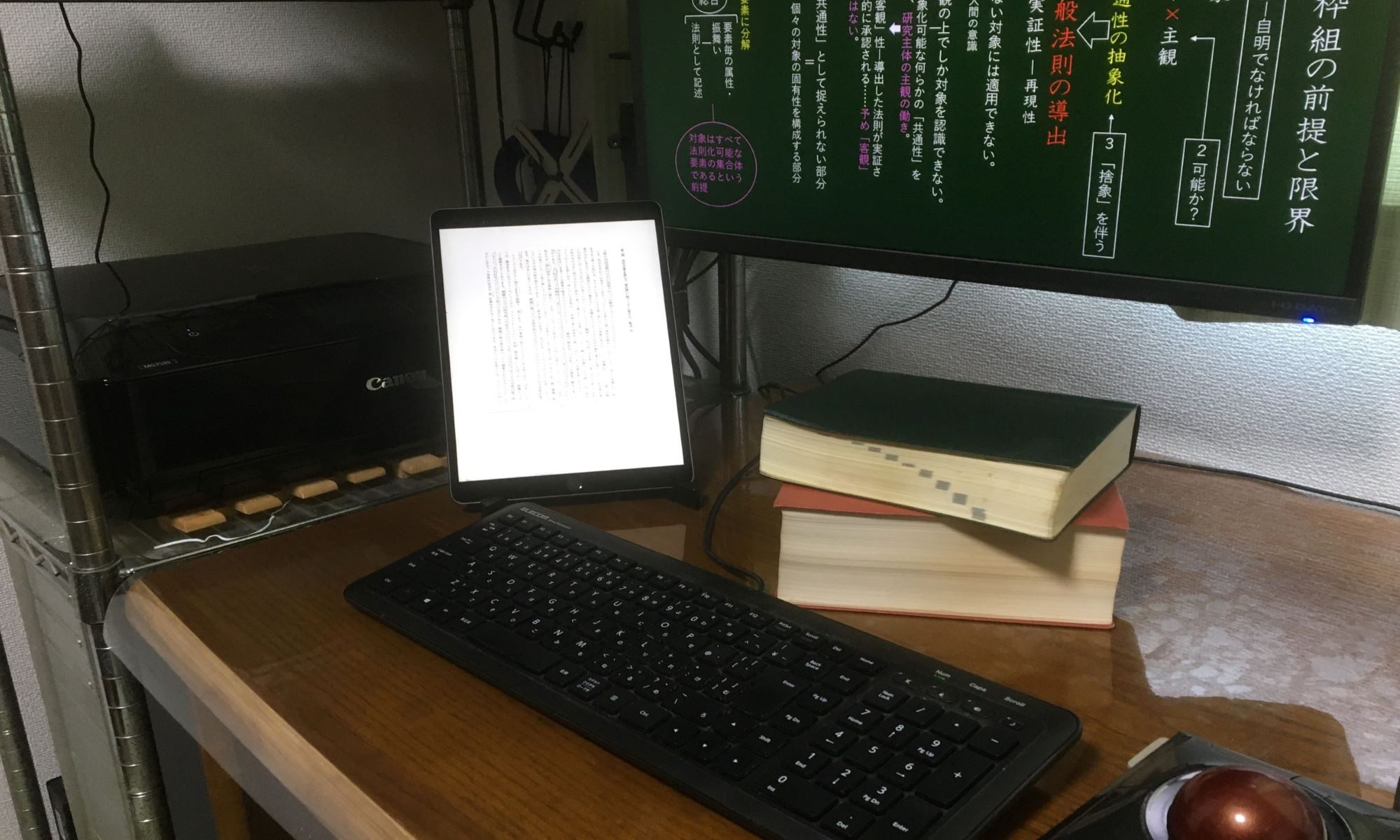読書の楽しみの一つは、何の疑問もなく自明視していたことについて新たな知見が得られ、必要に応じて認識を修正し、場合によっては世界観や人間観・歴史観が刷新されることだろう。もちろん自分の知識の生半可さや視野の狭さを思い知らされ、以前得意顔で喋っていたことが誤りだったり、きわめて一面的な判断だったことが白日の下に晒されて、穴に頭を突っ込んで死にたくなることも多いけれど。
伊藤正敏『アジールと国家』は、私にとって数十年ぶりに読んだ本格的「アジール本」である。数十年前に読んだのは言うまでもなく網野善彦『無縁・公界・楽』で、私もご多分に漏れず「アジール」という観念のもっている豊かな可能性に魅了されてしまった一人である。国家権力の処罰から逃走し、アジールに駆け込んだ者にはもはや国家権力の手が届かなくなるなどという物語は、管理と覗き見と訓練の大好きな近代国家の中で白土三平の劇画や石川淳の小説を愛読し、ロックという音楽のアナーキスティックな感性に心酔していた若者を、この上なくシビれさせたものだ。
『アジールと国家』を一読して、何といっても刮目したのは、中世の日本の歴史を動かした勢力として、公家と武家だけではなく「寺社勢力」という第三極が存在し、場合によっては世俗の権力(朝廷や幕府)を凌駕する、より上位の宇宙論的権威を振りかざして公家や武家の介入を拒否していたという指摘である。そのうえ寺社勢力の中心を担っていたのは僧侶や神官ではなく、「行人・神人」といわれる寺社の雑務を担当する下級の身分の者たちであり、彼らは自身が所属する特定の寺社の枠を越えて広範囲に活動し、行商や金融にも従事する一種の「経済体」を構成していたらしい。中世史を専攻したわけでもなく、公家・武家という二大勢力の角逐という教科書的で陳腐な中世史観しか持ち合わせていなかった私にとっては、目から鱗が落ちる思いであった。もしそうだとすれば、後の戦国時代の比叡山や石山本願寺、一向宗の絶大な権威の淵源の一端は、中世の寺社勢力のアジール機能にあるのだろうし、女子供まで標的にした信長の比叡山焼討ちや本願寺での虐殺の理由の一つもここに求めることができるのかもしれない。もしかしたら楽市楽座だって、行人・神人の経済活動を牽制(場合によっては邪魔)する目的もあったのかもしれず、秀吉の刀狩りがアジールの解体を目的としていた(これは本書で指摘されている)のなら、徳川幕府の寺社政策にも新たな光を当たる可能性が出てくるかもしれない。
とまあ放恣な想像はこれぐらいにしておいて、本書には他にも私が今まで気づかなかったことがいくつも指摘されていて、例えばヨーロッパ中世に比べて日本の中世のほうが圧倒的に一次資料が残されている(ヨーロッパ中世の王侯貴族の文盲ぶりと平安貴族以来の知識階級の筆まめぶりを考えれば実に納得できる)とか、江戸時代の儒者の排仏的歴史観がその後現代に至るまで歴史認識を規定している(つまり寺社勢力の存在を閑却し、公家と武家を中心に中世史を捉えることが自明視された)とか、とても勉強になる一冊であった。