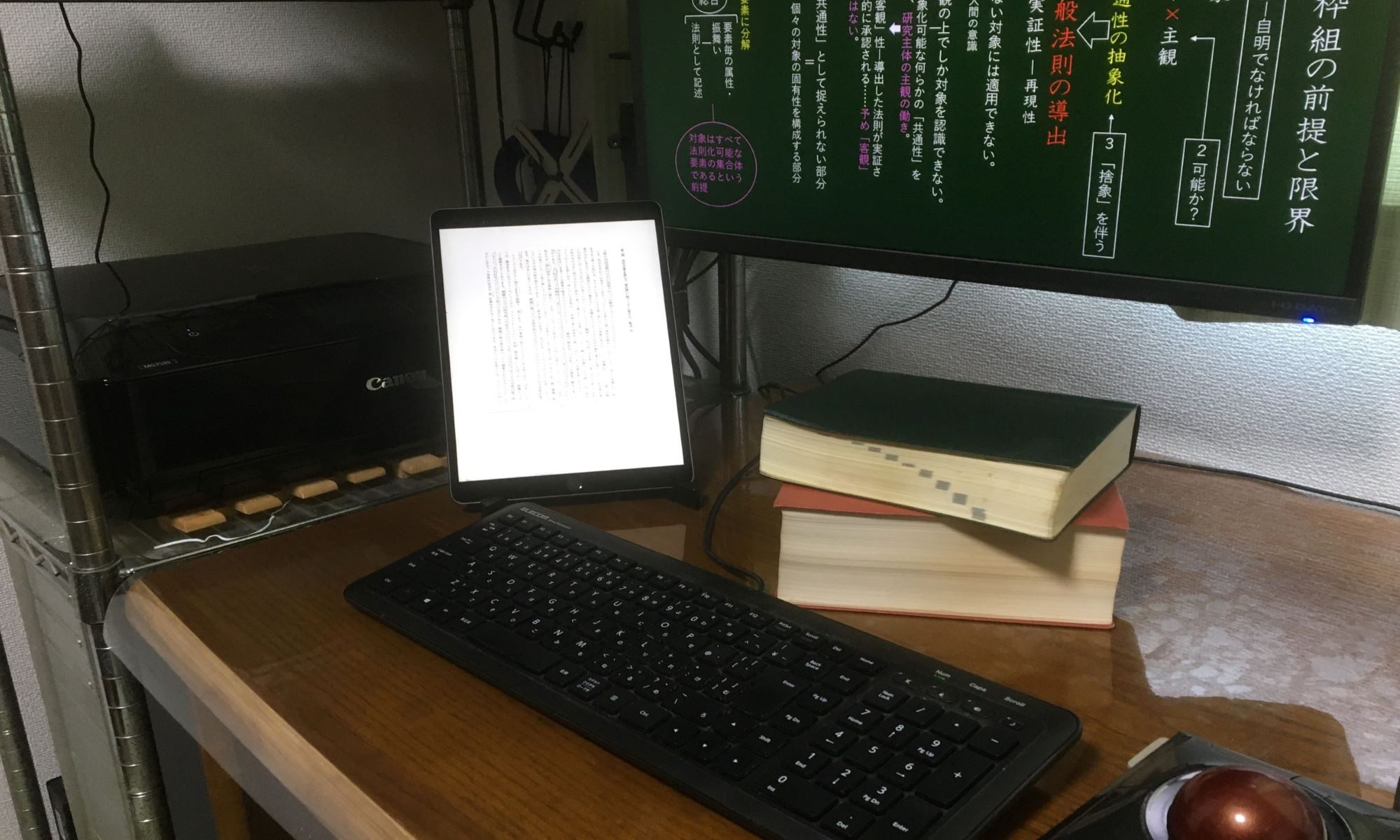学生の頃、上田秋成の『春雨物語』「天津處女」の中で、帝の目に留まらなかった五節の舞姫について「伊勢・加茂の斎(いつき)の宮のためしに、老いゆくまで籠められはてたまひき」とある部分に付けられた注釈に「伊勢の斎宮、加茂の斎院。天皇即位の時、未婚の王女から選んで、両宮奉祀の役としたもの。普通在位中仕え、独身を通す。」(日本古典文学大系『上田秋成集』中村幸彦注)と書いてあるのを読んで、この「独身を通す」が斎宮・斎院である期間の話なのか、秋成の文章にあるようにその後「老いゆくまで」なのか、疑問に思って調べてみようとしたのだが、何分知識も経験もない素人の悲しさ、何をどう調べればよいのか見当もつかず、そのまま忘れてしまった。
榎村寛之『斎宮―伊勢斎王たちの生きた古代史』はそんな長年の(?)疑問を解消してくれた一冊である。結論から言えば「独身を通す」のは斎宮・斎院でいる間だけで、天皇の代替わりや身内の不幸などで任を解かれた後は普通の皇族(内親王・女王)として暮らし、帝・親王・王や摂関家の男性に嫁いだりした人もあったそうだ。したがって『春雨物語』の記述は秋成の誤解か作り話ということになる。平安時代以降、斎宮・斎院のみならず内親王の結婚相手が激減し、結果的に元斎宮・斎院も未婚のまま過ごす人が圧倒的に多かった(本書59頁)ことから、そのような都市伝説みたいなものが語られたのかもしれない。
伊勢の「斎宮」というのは、正確には神に仕える女性「斎王」の居処兼役所で、多数の役人や諸国から租を運搬してくる人々などで賑わう一首の都市のようなものであり、本書『斎宮』は「方格地割」に区切られた都市構造、役所としての組織、経済的基盤、斎王の歴史的淵源や彼女たちの執り行う神事などについてかなり詳しく教えてくれるが、何といっても読んでいて面白いのは第2章「七人のプリンセス」第3章「斎宮年代記(クロニクル)」で紹介される、実在した斎王たちの伝記と逸話である。後に皇后となるも(恐らくは陥れられて)廃后の憂き目に遭い、死後に怨霊として畏れられた井上(いのえ)内親王、『源氏物語』の六条御息所と秋好中宮のモデルとなった「斎宮女御」徽子(よしこ)女王とその娘の規子内親王、神憑りを装って(?)託宣し、斎宮寮頭藤原相通と祭主大中臣輔親を手玉に取ったよしこ(「よし」は女偏に「專」)女王、『伊勢物語』の書名の由来ともされる、あの「狩りの使い」の話のモデル恬子(やすこ)内親王……。古代の斎王とその周囲の人物、時代との関わりが興味深い逸話とともに活写されていて、読者を飽きさせない。しかも朝原内親王の母、酒人内親王や徽子内親王、良子(ながこ)内親王、やすこ(「やす」は女偏に「是」)内親王などについては「美人であった」というウレしい情報付き。まさに至れり尽くせり。
それはともかくとして、後醍醐の治世を最後に斎王が置かれなくなったというのは示唆的である。もちろん本書172頁で触れているような天皇家の財政的破綻が大きな要因に違いないが、もう一つ、歴史的状況が斎王を必要としなくなったこともあるのではないかと思わせる。ヤマト王権は「複式王権」であった(象徴天皇制を採っている現在の日本もその変種かもしれない)。「複式王権」というのは祭祀を司る王(おもに女性)と行政軍事を統率する王(おもに男性)、という二種の王によって構成される王権であり、伊勢の斎王が祭祀王、天皇(あるいは朝廷や院)が行政軍事を担当する。武家から統治権を奪い返そうとする最後の試みが失敗した南北朝以後、現実の統治は将軍が担い、統治権の実質を失った天皇が祭祀王となれば、伊勢の斎王の存在理由はなくなるだろう。また南朝が偽の三種の神器を北朝に渡したという話にもあるように、この時期、王権の象徴としては「三種の神器」のほうが重視され、斎王の象徴機能はもはや必要なくなっていたのかもしれない。それに南北朝時代では二人の天皇、二つの朝廷。それぞれが斎王を派遣して、北朝の斎王一行と南朝の斎王一行が伊勢路で鉢合わせして大喧嘩の刃傷沙汰、というのではまるで町奴と旗本奴の男伊達競べやチンピラヤクザのショバ争いみたいで絵にもならないし。