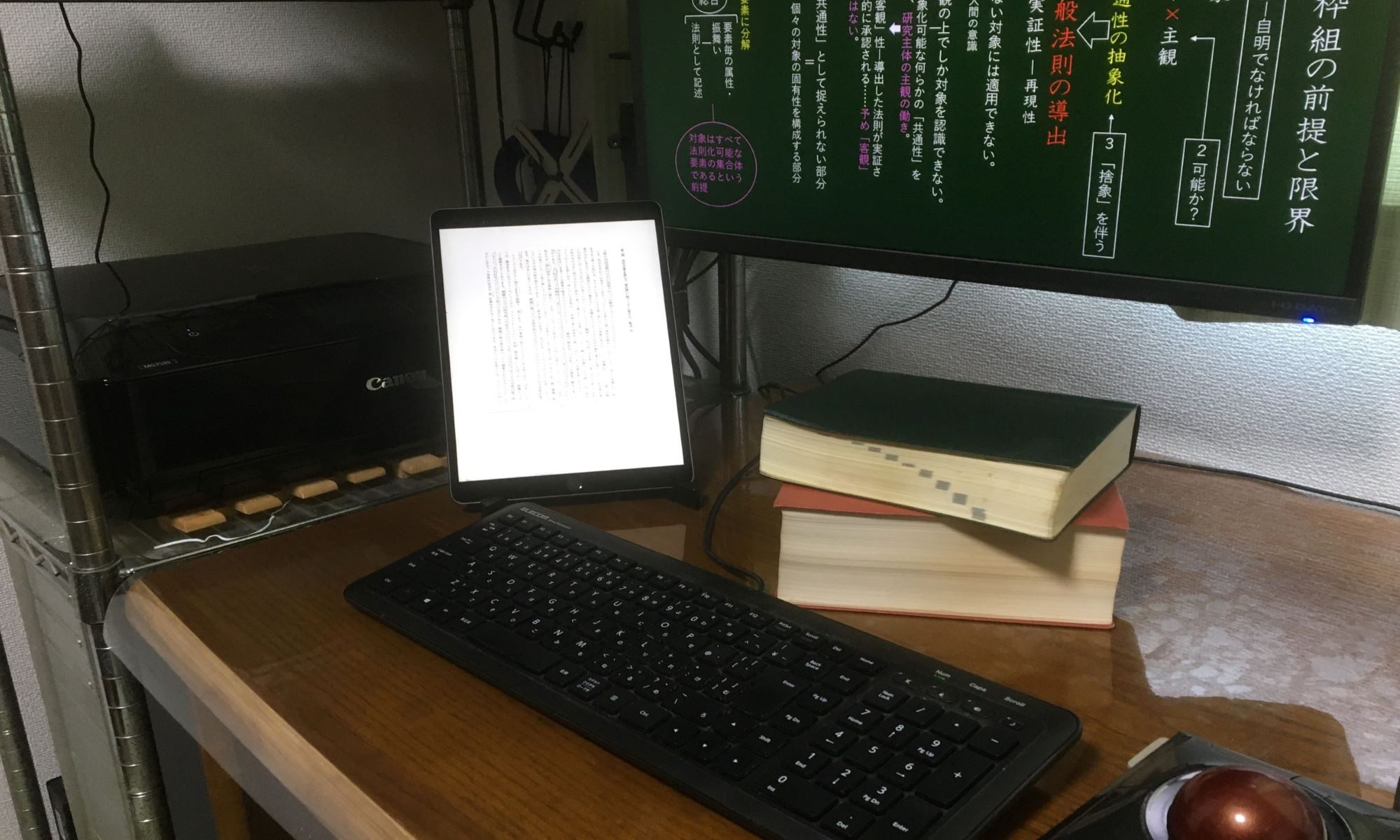最近、家で仕事をしている最中にはジャズ(おもにヴォーカル)を流していることが多い。以前からビリー・ホリディやサラ・ヴォーン、エラ・フィッツジェラルドなどは聴いていたが、ロック育ちである私がジャズを聴くことが多くなったのはいつ頃からだろう。
きっかけの一つは、数年前に同僚のある講師が、ニーナ・シモンのCDを貸してくださったことだと思う。『Here Comes the Sun』というアルバムだが、(おそらく私のロック好きを考えて)ビートルズやディランのカバー曲の入ったものを選んでくださったのだろう。聴いてみて非常に気に入った。中でも「Mr.Bojangles」は素晴らしかった。そこで彼女の主要アルバム二十数枚が収録されているMP3CDを入手したのだが、もっと早くから聴いておけばよかった。初期の『The Amazing Nina Simone』など、文字通り「アメイジング!」で、デビュー早々の作品とは思えない。ゴスペル、ブルーズ、R&B(ソウル)、いわゆるジャズだけではなく、私の好むブラック・ミュージックのほとんどを網羅する大変な歌い手さんであった。「対象がロック世代に限られているためジャズ、クラシックやオペラなどのジャンルは含まれていない(Wikipedia)」はずの米Rolling Stone誌「歴史上最も偉大な100人のシンガー」で、「ジャズ・シンガー」である彼女が29位に選出されているのも宜なるかな。
そんな彼女の歌の中で最も好きなのは「I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free」(1967)だ。
I wish I knew how it would feel to be free.
I wish I could break all the chains holding me.
I wish I could say all the things that I should say.
Say’em loud,say’em clear for the whole round world to hear.
という歌詞を見てわかるとおり、公民権運動を時代背景として歌われた曲(オリジナルは彼女ではないらしい)だが、そのような知識がなくとも、彼女の歌手としての力量が十分堪能できる曲である。
軽快で、しかし抑え気味に歌い出す前半から、曲の進行につれて徐々に盛り上がってゆく展開が見事で、シンプルなアレンジのバックが彼女の歌を効果的にサポートする。人の心を動かすのに過剰な装飾は必要ないということだ。同様に、よい音楽に冗漫な解説も野暮というものだろう。この曲の収録されているアルバム『Silk & Soul』には、他にも、後にダイアナ・クラールが歌う「The Look of Love」やノラ・ジョーンズが歌った「Turn Me On」なども入っている。機会があればぜひ一聴を。