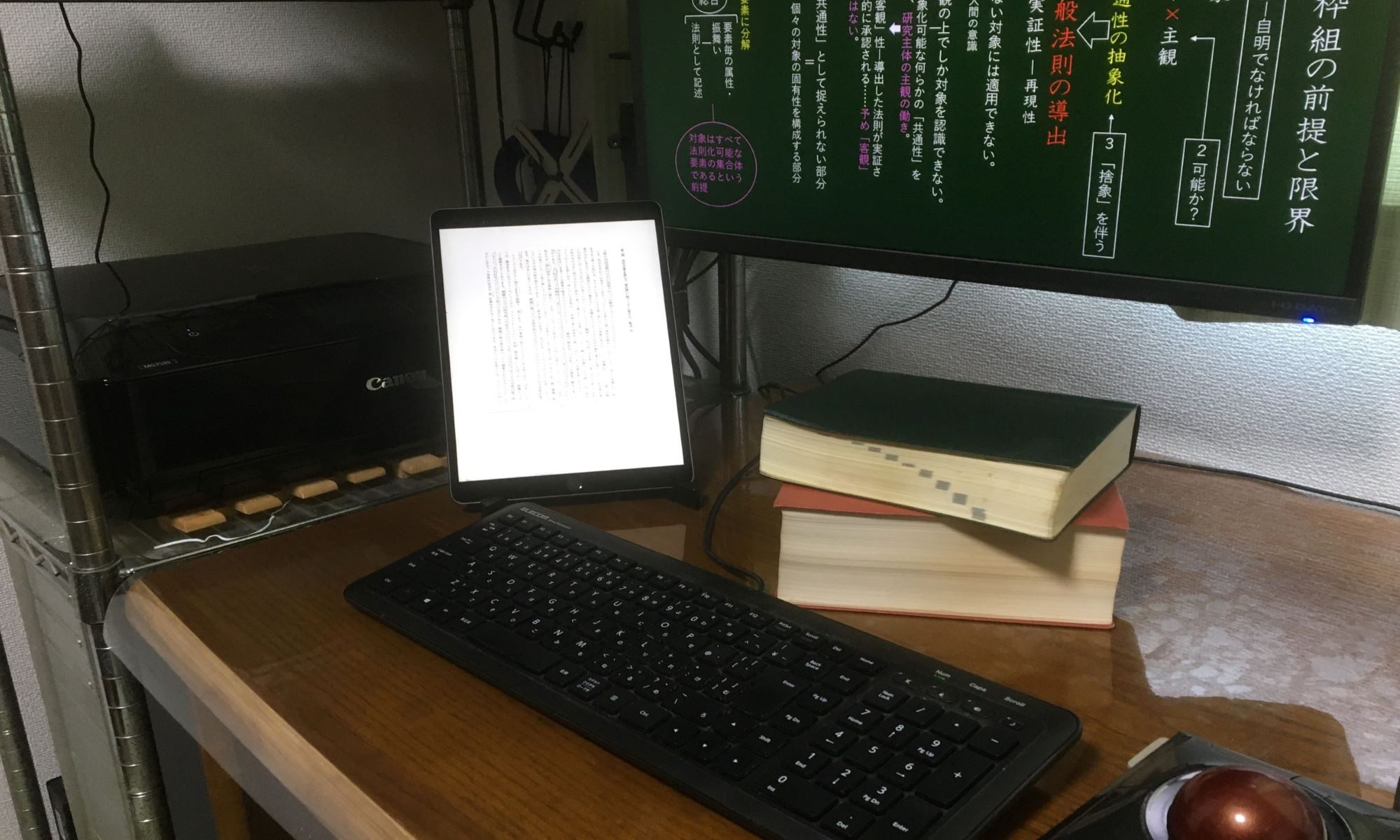「ドクター・フィールグッド」といっても、現在どれぐらいの人がこのバンドのことを憶えているだろうか。当時の日本の洋楽ファンでも、彼らを知っているのは少数派だったからなあ。なのでこのバンドのリー・ブリロー(Vo)時代のライヴを観たことのある日本人はそう沢山はいないと思う。自慢じゃないが私はその中の一人である。その時……したカセットテープに付けておいたメモを見ると、1980年11月8日(土曜日)発明会館ホール、とある。新譜『A Case of Shakes』の宣伝もかねて来日したのだと思う。この数年前にギタリストのウィルコ・ジョンソンが脱退し、替わりにジッピー・メイヨーという人がギターを弾いていたが、それ以外の三人、リー・ブリロー、ジョン・スパークス(B)、ジョン(ビッグ・フィギュア)・マーティン(Ds)はオリジナル・メンバーでの来日だった。
当時まだ高校生だった私は、「あのドクター・フィールグッドが来る」ということで友達に誘われて一緒に観に行った。たしか前座を務めたのは石橋凌率いるARB、客席には鮎川誠もいたように記憶しているが、客の数は多くはなく、決して大きいとはいえない会場の三分の一も埋まっていなかった。
メンバーがステージに登場し、スロー・ブルース・ナンバーを皮切りに演奏が始まると、前座のARBの時には石橋凌の挑発も虚しく体力を温存していた観客が一挙に大騒ぎ、最後にはみな自分の席を離れてステージの前で踊りまくっていた(もちろん私もその中でバカ騒ぎをしていた一人であったことはいうまでもない)。演出は極めてシンプル。派手なライトアップも、仕掛けもない。音楽のみで勝負。本当に楽しいライヴだった。そして今でも印象深く覚えているのは、フィールグッドの演奏中、ステージの袖のほうで真剣にそのパフォーマンスを見つめていた石橋凌の姿だ。偉大なる先輩バンドのステージから学ぼうとする真摯な姿勢が垣間見えた。
『Stupidity(殺人病棟)』はドクター・フィールグッド最大のヒットとなった(全英1位)1976年のライヴ・アルバムである。最大のヒット作であると同時に、このバンドの最高傑作だと思う。邦題の「殺人病棟」というのは原題とは何の関係もなく、日本で配給していたレコード会社の賢しら(例えば前作『Malpractice』にも「不正療法」というタイトルをつけて、フィールグッドを禍々しいイメージで売ろうとしたようだ)である。原題は収録曲のタイトルであり、この曲のオリジナルはソウル歌手ソロモン・バーク。キング・ソロモンの自己陶酔的でダイナミックな歌も私は大好きだ。
ブリローの力感溢れるヴォーカル、タイトなリズム・セクション。1曲目の「Talkin’bout You」からラストの「Roxette」まで、ノン・ストップで乗りに乗った演奏が繰り広げられる。中でも特筆すべきはウィルコ・ジョンソンの物凄いギター・プレイだ。派手なソロを弾くわけではないが、非常にメリハリのある細かいカッティングが持ち味のギタリストで、時に突っかかるような(モタる、ではない)タイミングのズレがかえって独特のドライブ感をもたらす。タイトル・チューンの「Stupidity」を聴いただけで、どれほどのギタリストであるか解るだろう。私もときどきギターをいじくり回すのだが、とてもじゃないがこんな風には弾けない(単に下手くそなだけとも言えるが、そのような不愉快なことは考えないようにしよう)。そんな演奏を、全編にわたってアドレナリン全開で続けるウィルコには、ほとほと感服する。以前このアルバムのウィルコの演奏について、誰かが「絨毯爆撃のようだ」と言っていたが、本当にそんな感じである。
と書いてくると、私が観に行ったのがウィルコの脱退後であったのが残念でならない。ジッピー・メイヨーがダメだというわけではない。この人も実力のあるギタリストで、後にヤードバーズに参加するなど音楽活動を続けていた。ライヴでの演奏は、当時の私も充分満足したし、今聴き直しても非常に良いプレイをしている。ただ、当り前のことだがウィルコとは持ち味が違う。おそらく60~70年代のシカゴ・ブルーズを基盤とすると思われるジッピーのギターに、ウィルコのような独特のドライブ感を求めるのは無理であろう。ブリローが鬼籍に入った今、もはや叶わぬ願いだが、一度でいいからブリローとウィルコの「ドクター・フィールグッド」を観てみたかった。
なお、ドクター・フィールグッドが登場したのは、イギリスの「パブ・ロック」といわれた音楽シーンの中からで、このパブ・ロックがその後のパンク・ロックの先蹤となったわけだが、パブ・ロックについてはウィル・バーチという人の『パブ・ロック革命』という本がある。