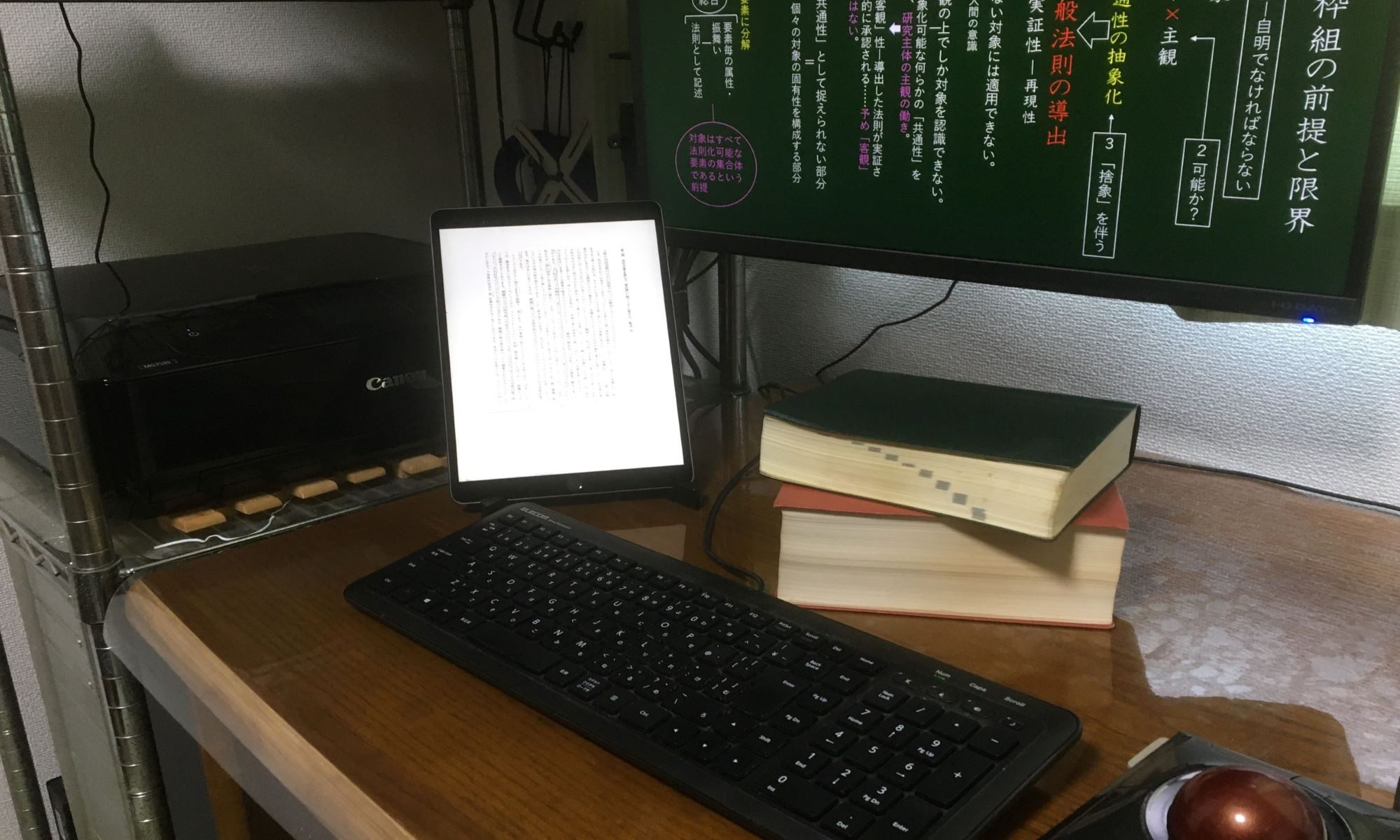子どものころ、とは言ってもロックを聴き始めたころだから中学生・高校生だったころ、私の周りの洋楽ファンの間で人気があったのはクイーンやレッド・ツェッペリンだった。私のようにストーンズやザ・フーを好んで聴いているのは少数派で、特にザ・フーのアルバムを持っていたのは私だけだった。もちろんクイーンやツェッペリンを嫌っていたわけではない(それが証拠に先年大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディ』で流れていた挿入歌は全部知っていたし、大学に通っていたころに観たライヴ・エイドでの圧倒的な演奏もよく覚えている)が、それよりも「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」や「サブスティテュート」のほうが格好良く聞こえたのだから仕方がない。
それにしても、ストーンズはともかく、ザ・フーは世界的なバンドでありながら、なぜか日本ではまったく人気がなかった。思うに、クイーンやツェッペリンの音楽はどこか大仰で、という言い方が悪ければ芝居がかっていて、様式的である。それに対してザ・フーの音は破壊的(「世界で一番やかましい演奏をするバンド」)であり、メンバー同士の仲も必ずしも良好ではなかった。この辺の違いは、ツェッペリンの「The Song Remains the Same(狂熱のライヴ)」とザ・フーの「Live at the Isle of Weight Festival(ワイト島ライヴ)」を見比べれば一目瞭然である。ツェッペリンはジミー・ペイジとロバート・プラントがアドリヴの掛合いを続けながらも決してステージ全体の様式を崩そうとしないが、ザ・フーは違う。メンバーそれぞれが、「自分こそ一番!」と言わんばかりにステージ上を暴れ回る。唯一動かないジョン・エントウィッスルは全身ガイコツがプリントされたボディスーツ姿で黙々とロック史上No.1の腕前のベース・ギターを披露している。その横ではロジャー・ダルトリーがマイクを振り回し、ピート・タウンゼントがギター抱えて跳び回り、キース・ムーンはどう見ても不必要なほどのオーバー・アクションで太鼓を連打する。音を消して映像だけ見たらほとんど××××を思わせるカオス状態である(そういえばステージ上で楽器やアンプを破壊するパフォーマンスはこのバンドが最初である)。それでいてドライヴ感に溢れた迫力満点の演奏で、当代一のライヴ・バンドの世評に恥じない見事さ。このブッ飛んだ感じが、当時の日本人の感覚に合わなかったのかもしれない。
そのようなバンドが、リーダー、ピート・タウンゼントのアイディアのもと、一致団結(?)して録音したのが『Who’s Next』だ。なんでもロック・オペラ『トミー』の大成功の余勢を駆って、ピートが『ライフハウス』という新たな企画を思いついたのだが、周囲の人に説明しても誰にも理解してもらえず(私も後年CDのブックレットに掲載されていたピートの言葉を読んだのだが、何を言っているのかさっぱり分からなかった)、仕方なくお蔵入り。その時に作った曲を核にアルバムを録音することになって、出来上がったのがキャリアの中でも最高傑作とされるこのアルバムだそうだ。1曲目の「Baba O’Riley」のイントロから流れるシンセサイザーのパターンは、当時ピートが傾倒していたバーバなんとかという導師の生誕をイメージしたものという話だが、そんなことはどうでもよい。この長いイントロ(1分以上ある)の途中からドラムス・ベース・ギターが唸り出すのだが、その瞬間の高揚感はロック特有のものである。そして注目すべきは、単調なシンセサイザーのパターンが、バンド全体のドライヴを支える効果を生み出していることだ。この効果はアルバムの最後を飾る「Won’t Get Fooled Again(無法の世界)」において最大限に発揮される。シンセサイザーのこのような使い方を思いつくとは、やはりピートは天才的アイディアマンであった。この曲での演奏の素晴らしさは特筆もので、四人のメンバーがその本領を遺憾なく発揮していると言ってよい。他の各曲も非常に魅力的で出来が良いのだが、やはりこの「Won’t Get Fooled Again」こそ(歌詞の内容も含めて)、ザ・フーのみならず、ロックという音楽を象徴する名曲であろう。
The Band『Music from Big Pink』(1968年)
「1967年か68年に聴いた一枚のアルバムが僕の人生を変えた。そしてアメリカの音楽をも変えた。」(ボブ・ディランのデビュー30周年記念コンサートでザ・バンドを紹介するエリック・クラプトンの言葉)
そのアルバムこそ、今回紹介するザ・バンド『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』(1968年)だ。もちろん私が聞いたのはその当時ではなく、もっと後になってからなので、発表当時どのような受け取られ方をしたかについて詳しく知っているわけではない。しかし、高校生のころはじめて聴いたこのアルバムは、充分に衝撃的だった。ポップなメロディーも、派手なギターソロも、爆発的な激しさもない。つまり一般受けする要素はほとんどないのに、一度聴いただけで、その音楽としての豊かさに圧倒されてしまった。以来数十年、折に触れては聴き続けている、私の愛聴盤である。
ザ・バンドは「カナダ出身」ということになっているが、音楽的な基盤は明らかにアメリカ南部のブルーズ、ゴスペル、R&B、そしてカントリーである。メンバーの中で唯一の南部出身者、リヴォン・ヘルムが彼らの音楽にどれほどの貢献をしたのかは、当事者でも何でもない私にはもちろん見当がつかないが、おそらく他のメンバーは彼から音楽に満ちた南部の生活(現代でも保守的で差別が常態化しているらしいバイブル・ベルトだが、この点だけは羨ましい)を教えてもらい、貪欲に吸収していったのであろう。これらのルーツ・ミュージックを完全に消化し(彼らの場合「解釈」という方が相応しいかもしれない)、音楽的素養の深さを感じさせるゆったりとした音世界で表現する。それを支えているのが彼らの卓越した演奏能力で、目立つプレイをするわけではないが、非常にしっかりとしていて安定感がある。後年のライブ・アルバム『ロック・オブ・エイジズ』で音楽ファンを驚かせた(なんせ現在のような音響技術のない時代の生演奏なのにスタジオ録音とほとんど遜色ないのだ)高い技術は、このデビュー・アルバムでも堪能できる。このアルバムの登場が当時の音楽に与えた影響の大きさも、なんとなく想像がつく。サイケデリック・サウンド全盛の時代に、このような土臭い音楽が、それも高い完成度で提示されたのだ。ロックのルーツであるブルーズ、ゴスペル、R&B、カントリーなどの音楽のもつ可能性を、すなわちロックという音楽の多様性と可能性とを示す事件であったのだろう。冒頭で紹介したエリック・クラプトンはこのアルバムを聴いてから、それまでの、つまりクリーム時代にやっていたようなインプロヴィゼーション合戦から、ルーツ・ミュージックに軸足を置いた音楽にシフトし、その後単に演奏家としてだけでなく音楽家として飛躍的に成長する。 また、1970年ぐらいからオールマン・ブラザーズ・バンドやレイナード・スキナードなどの、いわゆる「サザン・ロック」といわれるアメリカ南部出身のバンドが多数デビューし、その後のアメリカン・ロックの推進役となっていったのも、このアルバムの成功が大きな要因だったのだろう。
1976年の解散コンサートのドキュメンタリー映画『ラスト・ワルツ』(マーティン・スコセッシ監督)は、ちょうどジャズにおける『真夏の夜のジャズ』と同様、「ロック」という音楽自体を主役に据えた初めての映画だと思うが、そこでのインタビューを見ると、彼らがいかにロックとそのルーツ・ミュージックを愛しているかがわかる。ザ・バンドこそ、ロックの音楽的良心を体現したミュージシャンである。
近藤正臣主演『斬り抜ける』(1974~1975)
この、今となっては誰も知らないような地味なテレビ時代劇を発見したのは、名優・故岸田森の出演作品を調べていたときであった。主演近藤正臣、共演者も岸田森以外に和泉雅子、火野正平、志垣太郎、佐藤慶、菅貫太郎と、それなりに豪華だったので、TSUTAYAでDVDを借りて観てみたのだが、色々な意味で面白い作品であった。藩主(菅貫太郎)が病的な女好きで、家臣の妻(和泉雅子)を側女にしようと策謀して上意討ちを命じ、事情を知らないまま命令通りに親友を斬った侍(近藤正臣)が事の真相を知って、藩主のもとに連れ去られようとしている親友の妻を救出し、その息子ともども逃避行をするという話である。激怒した藩主は、真相を隠したまま二人に「不義者」という汚名を着せ、上意討ちされた家臣の父親と弟(佐藤慶と岸田森)を追っ手として差し向ける。同時に同じ松平姓の各藩主に回状を回して、江戸へ出て藩主の無法を幕府に訴えようとする二人を追い詰めようとするのであった……。
「時代劇にリアリティを」という志のもと制作された作品らしいが、「不義者の汚名を着せられ、逃亡する男女が徐々に互いへの愛を自覚してゆく」ようなかったるい作品に単純明快な(場合によっては物語の途中に中座して戻ってきてもわかる)筋書を好むテレビ時代劇のファンがついて行くはずもなく、低視聴率に苦しめられたらしい。その上放映途中に系列ネットワークが変更されるという事情もあってか、全二十話の物語の中盤で、大胆な路線変更を試みるのである。やっとのことで江戸に辿り着いた二人の必死の訴えも、幕府内の権力闘争の材料として利用されるにすぎず、その上なんと、和泉雅子(扮するヒロイン)が、岸田森(扮する義弟)に殺されてしまうのだ。和泉雅子といえば、私の幼少の頃の「綺麗なお姉さん女優」の代表的存在だっただけにとても残念で仕方がない(後年極地探検に凝り出した後の……については敢えて××××)。ヒロインの死後、真相を知った佐藤慶(扮する義父)は、息子夫婦の仇として藩主に刃を向けるが敢えなく討ち死に。佐藤慶に連れていかれたヒロインの忘れ形見も殺されたと思った近藤正臣(扮する主人公楢井俊平)は復讐の鬼と化し、菅貫太郎(扮する藩主)と、その後ろに控える江戸幕府に牙を剥く。番組タイトルも『斬り抜ける 俊平ひとり旅』と変更され、毎回藤田まことや小山明子、中村敦夫(ジャンゴよろしく棺桶を牽いて現れる)、中村玉緒、ジュディ・オングといった大物役者をゲストに迎えて、「リアリティを」という当初の志もどこへやら、尾張藩の城代家老暗殺、大阪城の金藏襲撃、身勝手で多情な姫君(将軍の娘)を晒し者に、と好き放題に暴れ回る(そういえば、日本刀は二人ほど斬ると血と脂が付いて切れなくなるので……とか、安物の刀は簡単に折れたり曲がったりしてしまう、という「リアリズム」も途中から無かったことになっている)。
路線変更後も視聴率は伸び悩んだらしいが、突如反権力闘争に舵を切るあたり、いかにも七十年代の作品である。藩主を斬り殺した所で物語が中途半端に終わってしまう(敵は江戸幕府ではなかったのか?)のも、視聴率だけではない様々な要因があったのかもしれないが、話が急に終わってしまう七十年代の低予算映画みたいだ。お世辞にも傑作とはいえないが、それでも、個々の役者は充分に持ち味を発揮している。主演の近藤正臣の少々大仰な演技(吉右衛門『鬼平』の初回の敵役の浪人もそうだが、この人は人間的な弱さを抱えた剣客みたいな役がよく似合う)も楽しいし、火野正平のお調子者役、佐藤慶の、一徹で家のためなら冷酷にもなれる剣客役なども良い感じであるが、やはり出色なのは岸田森である。妾腹の次男として生れ、つねに日陰者扱いされる(長兄の祝言の席にも呼ばれない)ルサンチマンを抱え、そのために陰湿冷酷で偏執狂的な、「日の当る場所」に出るためには手段を選ばない人物になってしまったという役柄を怪演している。中でも、自分が家督相続人となるため、義姉ばかりでなく父まで手にかけたのに、その望みが絶たれたときの表情など、実に素晴らしい。数少ない主演作の一つである『血を吸う眼』の和製ドラキュラ役を観ても、今さらながら早世が惜しまれる。
ウィルキー・コリンズ『月長石(The Moonstone)』(1968)
日本にも「世界に冠たる」という他愛ないナショナリズムを満足させてくれるものがいくつかあって、そのうちの一つが推理(探偵)小説の叢書だと思う。言うまでもなく創元推理文庫とハヤカワ・ミステリのことだ。私も若い頃、これらの文庫にはずいぶんお世話になった。ホームズにも、ポワロにも、サム・スペイドやフィリップ・マーロウにも、出会えたのはこの二つの叢書で日本語訳が読めるおかげであった。チャンドラーの造型した名探偵マーロウの、気障で泣かせるセリフのいくつかは、今でもおぼえている。だが、不思議なことに筋書、つまりどんな事件でどのような真相であったのかはほとんど記憶にない。これは(私が年を取ったからでは断じてなく)若い頃からそうなので、推理小説に限っては、読了後しばらく経つと、「面白かった」という感想のみが残って、内容についてはあっさり忘れてしまう。ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』も、クロフツの『樽』も、とても面白かったのに、今となっては筋書も思い出せない。私の頭が悪いせいだと思っていたら、二十年以上前であろうか、講師室でたまたまホームズものの話題になった時に、ある先輩の先生が、『まだらの紐』について、「『まだらの蛇』ってどんな話だったっけ?」とおっしゃって、思わずその先生に友情を感じてしまったものだ。そういえば、とある高名な作家も以前どこかで同じように、探偵小説は内容をすぐ忘れてしまう、と書いていた。とすれば私の頭が特に悪いから、というわけでもなさそうである。よかったよかった。
今回紹介するのは、そのように「中身は憶えていない」が、今まで読んだ推理小説で私を一番感心させた作品である。
ウィルキー・コリンズの『月長石(The Moonstone)』は文庫本で八百ページ近くになる長編であり、推理小説の古典的名作である。事件の五十年ほど前にインドで神像から略奪された世界最大級のダイアモンド「月長石」をめぐるミステリーだが、今回この文章を書くために読み返してみて、その出来の良さに再び唸ってしまった。経緯を経てその所有者となった退役軍人が、仲の悪い義妹の娘の誕生日に、そのダイアモンドを遺贈するところから事件が始まるわけだが、紛失したダイアモンドが再び発見されるまでの過程が、実に多様な登場人物の手記や報告書の形(つまり多数の登場人物の一人称による語りで)徐々に明らかになってゆく。この類の小説としては珍しいほどの長い物語だが、非常に緻密な構成と巧みな展開で読む者を飽きさせない。最終的に明らかとなる事件の真相も意外性に富んでいて(何といっても内容を忘れているのだから、再読しても楽しめた)、第一級の娯楽読物である。
ただし、この作品の最大の魅力は展開の巧みさや意外性ではない。それぞれの視点から事件を語る登場人物たちの魅力、言いかえれば優れた人物造型である。物語の舞台となるヴェリンダー家の令嬢(この人にダイアモンドが遺贈される)の一途さ、彼女の周りにいる男たちそれぞれの多面性、探偵役のカッフ部長刑事の妙な薔薇好きなど、どの人物も人間的な魅力に溢れているが、なかでもヴェリンダー家の老執事ベタレッジが素晴らしい。何かにつけて座右の書である『ロビンソン・クルーソー』から箴言めいた言葉を引用したがるこの老人は、その階級意識をも含めて、保守的で頑固だが同時に自ずからなるユーモアと優しさを兼ね備えた、愛すべき十九世紀イギリス人である。この点については私などが贅言を費やすより、丸谷才一氏による簡にして要を得た紹介があるのでそれを引用しよう。
「執事は善良であり、さまざまの人間的弱点を持っている。部長刑事は有能であり、しかし決して全能ではない。ぼくたちは思わず知らず、彼らとつきあっているような気になり、その結果、彼らが含まれている架空の世界全体を現実のものとして受け入れるのである。」(「長い長い物語について」講談社文庫『深夜の散歩』所収)
さて、今回は再読したばかりだから、さすがに内容を憶えていないということはないが、半年後にはどうだろうか。まったく自信がない。そこで老ベタレッジに倣って箴言を引用しておしまいにしよう。「われわれの忘却してしまったものこそ、ある存在をいちばん正しくわれわれに想起させるものである。」どこで読んだ言葉なのか、これも憶えていないが。
阪東妻三郎主演『魔像』(1952)
田村正和追悼(?)シリーズの二本目は、彼の実父阪東妻三郎の主演作『魔像』である。周知の通り、田村正和は阪妻の三男であり、兄の故田村高廣、弟の田村亮も俳優と、田村家は有名な役者一家である。因みに、顔立ちという点では正和が一番父親に似ていない。
阪東妻三郎こそ、20世紀の日本映画最大のスタアである。戦前の、まだ映画が「活動写真」だった無声映画の時代から活躍し、『雄呂血』『逆流』『無法松の一生』『狐の呉れた赤ん坊』『王将』『破れ太鼓』など、日本映画の歴史に残る数々の作品に主演、Wikipediaの記載に依れば、「1989年(平成元年)に文春文庫ビジュアル版として『大アンケートによる日本映画ベスト150』という一書が刊行されたが、文中372人が選んだ「個人編男優ベストテン」の一位は阪妻だった。死後35年余りを経て、なおこの結果だった。」
『魔像』は阪妻晩年の主演作だが、役者阪妻の魅力がよく分かる一本である。正直に告白すれば、観てからかなり時間が経っているので、筋書はほとんど忘れてしまった。たしか阪妻、この作品では一人二役をやっていたように記憶しているが、そんなことはどうでもよい。晩年の作品でありながら、彼が画面に現れた瞬間から、その姿と気風の良さに目を奪われる。役者の「華」とはこういうものか。それに較べれば、筋書の荒唐無稽さ(あるいは御都合主義ぶり)などたいした疵ではない。本物の「スタア」とは、脚本に合せて演技するのではない。「スタア」の魅力に脚本のほうが合わせるのである。これは、不世出の大スタア阪妻の格好良さを楽しむための作品である。
してみると、田村正和は(兄弟の中で顔立ちは一番似ていないが)父親の「華」の部分を最も色濃く受け継いだ息子だったのかも知れない。一流の役者でありながら、しかしどのような役をやっても「田村正和」でしかなく、かの『古畑任三郎』も、『刑事コロンボ』の枠組を使った本編の面白さもさることながら、冒頭の田村”任三郎”正和による導入(ナビゲーション)部分が作品の大きな魅力だったのだから。
三隅研次『眠狂四郎無頼剣』伊藤大輔脚本(1966)
田村正和の訃報を聞いて思い出した作品が二つあって、今回はそれを紹介したいと思う。但し、いずれも田村正和の出演作品ではない。
まず一本目は『眠狂四郎無頼剣』。田村正和も1970年代以降『眠狂四郎』を演じていたが、「狂四郎役者」はやはり何といっても市川雷蔵だ。雷蔵狂四郎の孤独と、冷たい色気は、他の役者にはない魅力である。しかし、十数本ある雷蔵狂四郎シリーズの中で、今回のネタ『無頼剣』は異色である。
この作品、従前からの「眠狂四郎」ファンの間ではかなり評判が悪い。それもそのはず、シリーズの他の作品(もちろん原作も)ではニヒリストの狂四郎が、この作品ではあろうことかモラリストとして登場するのだから。原作者の柴田錬三郎が激怒したというのも無理からぬ話だ。これは、脚本を担当した、戦前から活躍する大監督伊藤大輔が、「眠狂四郎」という枠組を借りて自らの思いを吐露した作品なのである。
実質的な主人公は天知茂扮する「愛染」と名乗る浪人で、彼は狂四郎の円月殺法と同じ剣の使い手である。大塩中斎の薫陶を受け、貧者の救済など社会正義の実現を目指していた彼は、大塩の乱の敗北などを経て幕府要路の人物の暗殺を企てるテロリストとなり、悪辣な手段で石油の利権を貪る豪商を脅迫している。ストーリーは面倒なのでここで紹介はしない(藤村志保扮する角兵衛獅子の芸人一行が絡んできたり、『蘆屋道満大内鑑』を元ネタにした謎掛けなどもあって結構複雑)が、この天知茂が素晴らしい。色気とユーモアを感じさせる演技で、主演の市川雷蔵を完全に喰っている。
私の世代にとって天知茂といえば、何といってもTVドラマ『非情のライセンス』の会田刑事であり、またテレビ朝日の『江戸川乱歩シリーズ』の明智小五郎である。若い頃は新東宝で中川信夫監督の『憲兵と幽霊』やら『地獄』やら『東海道四谷怪談』やらの、アクの強い役で勇名を馳せた人物である(それにしても『地獄』での演技はかなり大袈裟な感じがする。セットや特撮がチャチであるからかも知れないが)。なかでも『憲兵と幽霊』の悪役波島や石井輝男監督の『黄線地帯』の殺し屋役など、今でも強い印象が残っている。その彼が、やむにやまれずにテロに奔ってしまう浪人の哀しみを滲ませて狂四郎と対峙するのである。最後の手段として江戸市民を巻き添えにしたテロを計画するところまで思い詰めている天知愛染を前にして、これではさしもの雷蔵狂四郎も似合わないモラリストを演じてしまうのも仕方がない。
テロリスト愛染は、単に目的に凝り固まった平板なキャラクターとして登場するのではない。自分の秘密を探ろうとする女(藤村志保)に対しては警告を与えながらも紳士的に応対するし、脅迫相手の豪商の、頑是ない娘にはあくまでも優しく、死の間際まで彼女との約束を果たそうとする。お決まりのように狂四郎の剣に斃れた愛染が、末期の願いとして狂四郎に託そうとする、豪商の娘に贈る約束だった手製の竹人形が、事切れた彼の手からこぼれ、屋根の上を滑り落ちてゆくシーンは、その幼い娘が彼の思いを理解する日など永遠に来ないだろうことをも暗示しながら、この上なく哀切である(三隅研次の演出が素晴らしい)。戦前、まだ露骨な統制の対象とならなかった時代の映画屋たちのアナーキーな雰囲気と、失敗に終わった、つまり結局は国家権力システムの好餌となってしまったテロの実行者たちの「真情」――かつて石川啄木が「われは知る/テロリストの かなしき心を」(『呼子と口笛』)と詠った「心」。おそらく伊藤大輔はそれらの「記憶」を胸にこの作品の脚本を練ったのであろうと、勝手に想像する。
アラン・ムーア『フロム・ヘル』(1989~2004)
私はあまり漫画を読まない。また流行っているから飛びつくという種類の人間でもないので、話題の『鬼滅の~』とやらが『どろろ』とどう違うのかも知らないし、最近の『ワンピース』『進撃の巨人』『キングダム』など、題名しか知らない。かといって漫画を嫌っているわけでもなく、まったく読まないということでもない。先年、蔵書のほとんどをPDFファイル化(いわゆる「自炊」というやつ)した際、漫画本が二、三百冊出てきたので、少しは読んでいるし、子どもの頃に流行った『あしたのジョー』『巨人の星』『がきデカ』『ドカベン』なども一通り知っている(歳がバレるね)。とはいえ、やはり詳しいわけではない。四十代以後は信頼できる人が褒めている作品を時々読むばかりである。そうやって読んだのがたとえば『攻殻機動隊』であり、『沈黙の艦隊』『ザ・ワールド・イズ・マイン』である。どれも非常におもしろかった(それにしても最近の作品がないね)。そのような私が、先日数年ぶりに再読して性懲りもなく再び感心してしまった漫画(「コミックス」というべきか)がアラン・ムーア『フロム・ヘル』である。
時は1888年のロンドン、王子の火遊びに端を発して、さまざまな立場の人間のさまざまな思惑が絡み合い、五人の娼婦が次々と惨殺される……。そう、史上最も有名な連続殺人鬼「切り裂きジャック」の事件を素材とした作品である。ただし、よくある「犯人捜し」を趣旨とした著作ではない。事件の犯人や動機の大枠については、スティーブン・ナイトという人の『切り裂きジャック最終結論』(成甲書房:Jack the Ripper;The Find Solution 1977)に依っているが、ムーアはナイトの説を支持しているというより、物語を構想するのに都合のよい枠組として利用したということのようだ。
丁寧に施された伏線、重層的で緻密な構成の物語叙述、神話的・魔術的な認識(フリーメイソンが重要な役回りを演ずる)を通じて、ムーアは十九世紀末のイングランド社会のみならず、ローマ帝国がブリテン島を支配する以前の時代から二十世紀に至るヨーロッパの歴史を、文明の物語を、圧倒的な迫力で幻視する。ムーアは巻末に附された「注解」の中でこう述べる。
「私には、多くの点で1880年代に20世紀の種がまかれたように思われる。政治とテクノロジーだけではなく、芸術と哲学の分野でも。1880年代が20世紀の本質をはらんでいたという考え。そしてそれと同時にホワイトチャペル連続殺人こそが1880年代の本質をとらえていたという思いが本書の中心的アイデアとなっている。」(柳下毅一郎訳)
いうまでもなく、十九世紀はヨーロッパ文明のひとつの到達点であり、続く「殺戮の世紀」二十世紀の序章とも言われるホワイトチャペル連続殺人事件を結節点として、その後のヨーロッパの衰退をも包み込んだ宇宙を表現しようとしたかのようだ(「議論の余地なく神々が存在する場所、それは我らの精神の中だ」――『フロム・ヘル』第四章、ウィリアム・ガルの言葉)。再読三読に耐える、紛うことなき傑作である。
訳者の柳下毅一郎(因みに、この人物は私がもっとも信頼する映画評論家である)によれば、アラン・ムーアは「欧米コミック界でもっとも尊敬され、もっとも恐れられている天才」なのだそうだ。この人の作品では他に『V・フォー・ヴェンデッタ』『ウォッチメン』も読んだ。いずれも非常におもしろかったが、やはり『フロム・ヘル』が一番だ。ただし、映画化作品はむしろ清々しいほどにこの作品の長所を削ぎ落とした、独自性に溢れる凡作なのが残念である。
このブログについてのご案内
受験塾のHPの宣伝ブログであるにもかかわらず、受験情報も勉強法の類も出てこないのを不審に思う人もいるかもしれないので、ここで説明をしておこう。誰も読まないだろうけれど。
このブログを始めるにあたって決めた基本方針は以下の通りである。
① 自分の好きなこと、気に入ったものについて書く。
納得できないこと、腹の立つことについて書くのはたやすいが、そのようなものを書いたところで事態が好転するわけでもなく、何の益にもならないどころか、逆に批判している自己に酔って独善に陥る可能性が高い。世に「盗人にも三分の理」というが、たとえ批判されてしかるべき人物であってもそれなりのよんどころない事情があるかもしれず、事情もよくわからないままいい気になって批判して、後で後悔するのも嫌である。それにたとえば近年の文部科学省だの有識者会議だのの迷走ぶりについては、言いたいことが山ほどあるが、それを書きはじめると、書いているうちにどんどん腹が立ってきて、怒りのあまり腹が減ってしまう。詰まらぬことだ。
自分の気に入ったものについて、その魅力を伝道している方が気が楽である(つまり書いても書かなくてもよい、無駄な文章だから更新も遅くなるのである)。
② 時事問題は扱わない。
時事問題は、いうまでもなく現在進行中の事象であり、必然的に全貌を捉えることが難しく、どのような結果になるのかも不明である。そのような問題について、わかったような顔をして御託を述べるのは、知性ある人間の取るべき行動ではない(という気がする)。そして何より、一過性の話題などについて駄文を綴るより、アラン・ムーアの『フロム・ヘル』でも読んでいた方がよほど楽しい。
③ 受験情報や勉強法などは話題にしない。
受験情報などはこんな個人塾より学校や大手予備校のほうが早くて正確だし、勉強法について、タダで教えてあげられる内容はタカが知れている。こちとらも商売なので、全部をブログで公開するわけにもゆかないのである。そして勉強法は、中途半端に一部分だけ教えても役に立たないどころか有害でさえある。今までどれだけ「~すれば成績アップ!」という文句に踊らされている受験生を見てきたことか。
ということで、今後も好きなことを好きなように(気が向いたときに)書き綴ることと致そう。
マデレーン・オルブライト『ファシズム 警告の書』
今回の言わずもがなのお喋りのネタはマデレーン・オルブライト『ファシズム 警告の書』(2019)である。ムッソリーニ、ヒトラー、スターリンといった、言わずと知れたファシズム史の「スター」の行跡の紹介・分析を経て、戦後から現代に到るファシスト的政治家の人物伝、という趣の書だ。たとえばハンナ・アーレントの名著『全体主義の起源』のように、「反ユダヤ主義」や「植民地主義」などファシズム運動をもたらした歴史的背景を丁寧に分析するわけではなく、またW.ラカーの『ファシズム 昨日・今日・明日』のような、世界中に広汎にみられるファシズム的運動の紹介・分析を主眼とした書でもない。過去のファシストについて特に目新しい知見が示されているわけでもないが、しかし、現代が新たなファシズムの時代の予兆と思えるようなサインに満ちた時代であることが実感できる、必読の書である。著者がこの書をものした契機がトランプ政権の登場であることが序文で触れられているが、なにもこの張子の虎(ンプ)だけではない。自己が疎外されていると感じる人々が多数存在する社会は、アメリカだけではないだろう。ファシズムはそのような状況で人々の心のなかに兆してくる欲動を餌に、(人々の気持ちを代弁するかに装って)成長するという「常識」をもう一度銘記する必要があるだろう。特に政府が無策な、あるいは腐敗している国家においては要注意である。どことは言わないが。
ファシズムというのは難しい概念で、「人の数ほど定義がある」といっても良いくらいだ。それもそのはず、「カント哲学」「実存主義」「構造主義」などと違って、「ファシズム」という具体的な思想は存在しない。『ファシズム 警告の書』にはこうある。
「私(マデレーンおばさんである)が考えるファシストとは、特定の集団や国家に自分を重ね合わせてみずからをその代弁者とみなし、人々の権利に無関心で、目標達成のためには暴力も辞さずにどんなことでもする人物だ。」(白川貴子・高取芳彦訳)
これを筆者流に解釈すれば、特定の集団や国家の標榜する理念をあたかも救世主であるかのように賛美し、権威主義的にそれへの同調を(ときに暴力を以て)他者に強要、その内面まで規制して国家・集団への奉仕を求める人物、ということになる。つまり国家・集団の唱える主張の具体的な内容(それは民族主義でも共産主義でも、他の主張でもあり得る――もしかしたら民主主義を騙るかもしれない)は問わない。「ファシスト」は実在しても具体的内容を伴った「ファシズム」という思想は存在しない。「ファシズム」とはむしろ、そのような人物や集団の行動様式をいう言葉なのだろう。
著者のマデレーン・オルブライトはチェコスロヴァキア出身のユダヤ系アメリカ人なのだそうだ。幼い頃からファシズム(ナチスとスターリン)の弾圧を逃れて家族とともに2度も亡命した経歴を持つ人で、いくら父親が外交官だったとはいえ、そのような中で学問に勤しみ、第2次クリントン政権でアメリカ史上初の女性国務長官となった人なのだから、いかに優秀な人物であるかわかるだろう。『ファシズム 警告の書』後半の、国務長官時代に交渉の機会をもったユーゴスラヴィアのミロシェビッチ、ロシアのプーチン、トルコのエルドアンなど、ファシスト的傾向をもった政治家についての観察、分析は非常に鋭いものを感じさせる。たとえばプーチンについて「プーチンは完全なファシストではない。そうなる必要を感じていないからだ。その代わり、首相や大統領として、スターリンの全体主義の教科書をめくり、都合良く使えそうな部分にアンダーラインを引いてきた。(中略)プーチンの望みは、自らの統治下にある人々に、彼が政治的に無敵の存在だと信じ込ませることだ。困難(あるいは危険)を顧みない潜在的な政敵が全国規模の本格的な対抗勢力を結集することのないよう、その気勢を削ぐことにいつも力を費やしている。(中略)プーチンは自らの魅力を維持するため、特定のイデオロギーや党派と深く結びつくことを避け、国全体の顔としてのプーチン像を描こうとしている。」(下線は筆者による)
このような、海千山千の妖怪が相手である。親愛なるわが国のス×ーリンでは少々役者不足かもしれない。
ドクター・ジョン『Duke Elegant』(1999)
ドクター・ジョンのアルバムは30枚ほど持っているが、中でも一番聴いた回数が多いのはこの『Duke Elegant』であろう。アルバム・ジャケットに「PERFORMING THE MUSIC OF DUKE ELLINGTON」とあるように、かのデューク・エリントンの曲のカヴァー・アルバムである。初めて聴いたときの印象は、「カッコいいアルバムだなあ」。ドラムス、ベース、ギター、ピアノ(オルガン)というシンプルな構成(一部サックスやパーカッションが参加している)で、バックの締まった演奏の上でピアノの、ギターの、そしてサックスの自在なアドリブが堪能できるアルバムである。
アルバムの印象は……
全体にファンキーな仕上がりになっているのはドクター・ジョンの持ち味なので当然といえば当然だが、「Caravan」「Mood Indigo」「It Don’t Mean a Thing(If It Ain’t Got That Swing)」(スウィングしなけりゃ意味ないね)などの有名曲に大胆な解釈を加え、それらの曲のオーソドックスな演奏とはまったく印象の違う演奏を披露してくれる。
私はそれほどジャズを熱心に聴いておらず、また詳しいわけではないので、オープニング・ナンバーの「On the Wrong Side of the Railroad Tracks」、続く「I’m Gonna Go Fishin’」、そして最後の「Flaming Sword」の3曲はこのアルバムで初めて耳にした。このアルバムの性質上、オーソドックスな演奏とかけ離れたアレンジである可能性もあるが、3曲とも実に魅力的である。まずオープニング曲「On the Wrong~」がファンキーでソウルフルなムードたっぷり。この手の雰囲気が大好きで、思わずワイルド・ターキーの瓶に手を伸ばしたくなる私としては、開始早々ノックアウトされてしまう。次の「I’m Gonna~」での聴きモノは、チョッパーを多用したベースの「スウィング」とワウの聴いたギターのアドリブ、さらにエンディングのたどたどしいコーラスの微笑ましさである。バックのロウワー9の連中は、楽器の演奏は非常に上手いが、歌は得意でないらしい。さらに上記のような有名曲が並んでゆき、ラストの「Flaming Sword」でちょっとした「奇蹟」が起こる(大袈裟か)。
直前の2曲「Things Ain’t What They Used to Be」「Caravan」が、比較的ハードなアレンジであることもあってか、ラスト・チューンのイントロが流れ始めると、一種爽快な解放感を感じるのだ。ポップなメロディーと、相変わらずファンキーでタイトなバックの演奏、そしてドクター・ジョンの、ボールが転がり跳ねるような自由で躍動感のあるアドリブ。アルバムを聴き終わったときには、なんだかとても幸福な音楽体験をしたような余韻に浸れる。
他人の曲も自家薬籠中のものにできるのはレベルの高い音楽家だと思ふ
ドクター・ジョンはこれ以前にも、1989年のグラミー賞受賞作『In a Sentimental Mood』、1995年の『Afterglow』といったスタンダードのカヴァー集でデューク・エリントンの曲を何曲かカヴァーしている。しかしこのアルバムで見られるほど思い切った楽曲解釈を示したわけではなかった。稀代の歌姫エラ・フィッツジェラルドがデューク・エリントンとそのオーケストラをバックに従えて作ったアルバムで、「Duke Elegant」全13曲のうち9曲が共通するエラ・フィッツジェラルドのソングブック「Sings the Duke Ellington Song Book」(これも素晴らしい)と聴き比べてみると、ドクター・ジョンがエリントンの曲を完全に自分のモノとして消化し、その上で自分の個性を存分に発揮していることが解る。彼にはそのほかにジョニー・マーサーのソングブック「Mercernary」(2006)、ルイ・アームストロングのレパートリーを演奏した「Ske-Dat-De-Dat: The Spirit Of Satch」(2014)もあり、特に後者は聴いていてとても楽しい気分になるアルバムだ。